
こんな先生・教授から学べます
地域における積極的な社会参加を促し、交流につなげる先生
さまざまな立場の人が、社会活動に参加しやすい地域社会の実現をめざす「地域福祉論」を専門とし、現在はボランティアにおけるインセンティブについて研究しています。「ボランティア」というと、一般的には自発的かつ善意による支援活動と認識されることが多いように、参加者の主体性が最も重んじられます。しかし、人々の生活課題の複雑化やそれに伴う支援活動の多様化とともに「有償ボランティア」という概念が現れました。有償とは必ずしも金銭報酬に限らず、活動に必要な物品の購入や交通費など、活動における負担を軽減し、より多くの人がボランティアに参加しやすくなるための支援も含まれます。当事者であるボランティアの参加者が活動をどう捉え、どのような支援を求めているのかを調査し、よりよい社会参加につなげていきたいと考えています。

研究の中心はアンケート(量的調査)とインタビュー(質的調査)。これらの手法は学生のゼミ活動にも活かされる
フィールドワークや、地域サロンへの参加をはじめとした実践と交流、そして学生の主体性を重んじる守本ゼミ
学生の志向に応じて、さまざまな研究手法を学べる守本ゼミ。なかでも重視しているのが、フィールドワークや、地域の交流の場である「ふれあい・いきいきサロン」への出前講座といった地域での学びです。出前講座はゼミにおける「実践活動」の一環として行われ、クイズ形式による脳機能トレーニングや、スマホ教室を展開。トレーニングに用いるクイズの作成やスマホ教室の運営は学生主体で行われ、世代を越えた交流を通して異なる価値観にふれることで、社会福祉の根幹である「相手を知り、相手に合った支援を行う」ための視点を養います。

クイズに用いるアイデアはすべて学生発。季節や対象者の年代なども考慮した題材を用いることで交流も活発に
いろいろなことに興味をもち、積極的に関わることがあなたの世界を広げます
社会福祉の基本的な考え方は、相手を尊重することです。また人を思いやり、支え合い、高め合うことは、福祉に限らずさまざまな分野で活かせるもの。ぜひいろいろなことに興味をもち、積極的に関わってみてください。

学生時代には自閉スペクトラム症の子どもと関わるボランティアに参加。交流が新たな活動につながったという
守本 友美教授
専門分野/地域福祉、ボランティア論、ソーシャルワーク理論
略歴/神戸女学院大学大学院でソーシャルワークを学び、社会福祉法人大阪ボランティア協会でボランティアコーディネートに携わる。看護・リハビリテーション等の専門学校で非常勤講師を務めた経験から、後進の指導に強いやりがいと福祉教育の意義を感じ、教育の道へ。広島国際大学等で教鞭をとる。2022年より現職。博士(医療福祉学)。
※この画面の情報は、すべて取材した時点でのものになります。
この学校のおすすめ記事
-
 卒業後大切なのは、想いに寄り添うこと。一人ひとりに行き届いた支援を行えるようになりたい福祉情報学部 人間コミュニケーション学科 卒 社会福祉士(ソーシャルワーカー)
卒業後大切なのは、想いに寄り添うこと。一人ひとりに行き届いた支援を行えるようになりたい福祉情報学部 人間コミュニケーション学科 卒 社会福祉士(ソーシャルワーカー) -
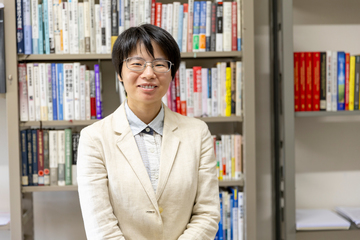 先生・教授グローバルビジネスによる中国経済の可能性を追究する先生経済経営学部経済経営学科 エイ デイ(WEI DI)先生
先生・教授グローバルビジネスによる中国経済の可能性を追究する先生経済経営学部経済経営学科 エイ デイ(WEI DI)先生 -
 在校生驚きと発見に満ちた毎日。学び、生活、人間関係全てが楽しい!経済経営学部経済経営学科
在校生驚きと発見に満ちた毎日。学び、生活、人間関係全てが楽しい!経済経営学部経済経営学科 -
 在校生生まれ育った地域で、多様な視点から子育て世帯を支援できる存在に人間健康科学部福祉学科
在校生生まれ育った地域で、多様な視点から子育て世帯を支援できる存在に人間健康科学部福祉学科
