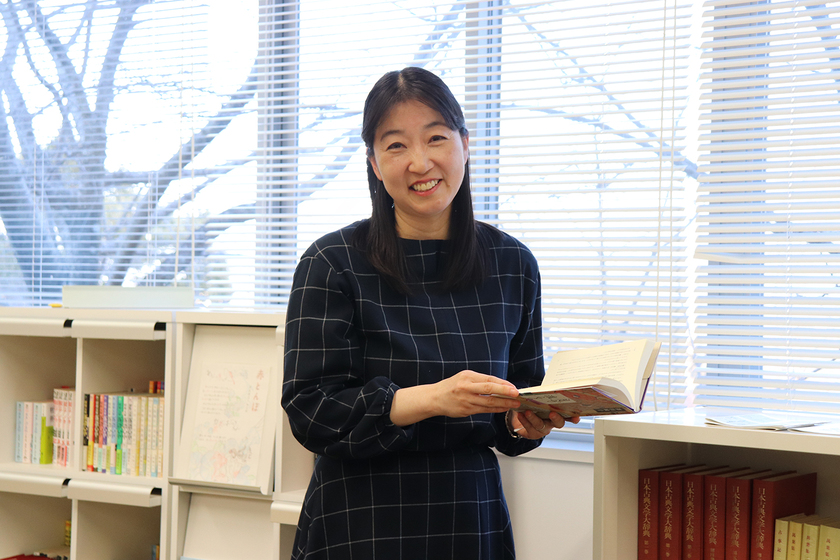
こんな先生・教授から学べます
日本文学の研究や創作を通して学生の成長を支える先生
日本近世文学の人形浄瑠璃や歌舞伎を中心に研究しています。作品が生み出された時代の歴史を学び、役者絵や上演記録などのさまざまな資料を調査・分析することで、やっと見えてくるものがあります。たとえば近松は作者修業時代、歌舞伎の「道具直し」をしていたという記述があります。「道具直し」の用例を集め、当時の歌舞伎に関する資料を調べると、観客の前で道具の位置を動かす役割であったことがわかりました。若き日の近松が演劇の現場である舞台に出ていた姿が浮かび上がります。複数の視点からの分析を積み重ねることで当時の人の姿を生き生きとイメージでき、その人の想いに触れる感覚を持つことが豊かな喜びにつながります。私自身、学生の意見から気づかされることも多く、意見を分かち合いながら研究する楽しみも感じています。

資料の解読にあたり学生の相談を受ける後藤先生。学生ならではの豊かな感性が調査研究のヒントになると話す
プロの作家や編集者による指導で、創作スキルだけでなく人間的にも成長
創作文芸・出版プログラムでは、学生たちが創作活動に取り組んでいます。小説を創作し、編集を行って冊子を完成させるほか、古書を販売する古書市も開催し、収益を子どもに本を贈るチャリティーに寄付しました。このプログラム最大の魅力は、直木賞を受賞した作家や編集者から貴重なお話を聞き、直接指導を受けられること。プロの優しく丁寧な指導に刺激を受け、学生たちの表情はイキイキと輝いていきます。おとなしい性格の学生も積極的に創作に取り組むようになり、就職活動にも意欲的になるなど、人間的にも大きく成長しています。

プロの作家や編集者の指導、仲間との意見交換などで楽しく成長が実感できる創作文芸・出版プログラム
文学を読む喜びが何倍にも大きく膨らむ出会いがあります!
文学を主観で読む楽しみに、客観的な分析を積み重ねることで、作者の想いに触れる喜びが感じられます。学生同士での協働や作家や編集者からの直接指導などを通じて、学生生活を充実させてもらえたら嬉しいです。
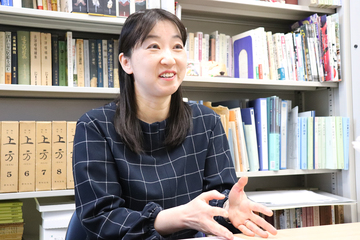
後藤 博子 教授
大阪市立大学文学部国語国文学科卒業。大阪市立大学大学院文学研究科国文学専攻後期博士課程修了、博士(文学)取得。2008年歌舞伎学会奨励賞受賞。2011年より本学日本文化学科准教授として着任し、江戸時代の演劇を中心に文学を研究。司書課程や創作文芸・出版プログラムも担当している。
※この画面の情報は、すべて取材した時点でのものになります。
この学校のおすすめ記事
-
 在校生歴史の魅力を感じる学びが充実!学芸員になるのが今の目標です文学部 日本文化学科
在校生歴史の魅力を感じる学びが充実!学芸員になるのが今の目標です文学部 日本文化学科 -
 先生・教授古代の瓦をヒントに新たな歴史的事実を発見する先生文学部日本文化学科 清水 昭博教授
先生・教授古代の瓦をヒントに新たな歴史的事実を発見する先生文学部日本文化学科 清水 昭博教授 -
 先生・教授名もなき武士の文書から歴史の真実を読み解く先生文学部日本文化学科 花田 卓司 准教授
先生・教授名もなき武士の文書から歴史の真実を読み解く先生文学部日本文化学科 花田 卓司 准教授 -
 在校生子どもたちの「学びたい」という気持ちに寄り添える、社会の先生に!文学部 日本文化学科
在校生子どもたちの「学びたい」という気持ちに寄り添える、社会の先生に!文学部 日本文化学科
