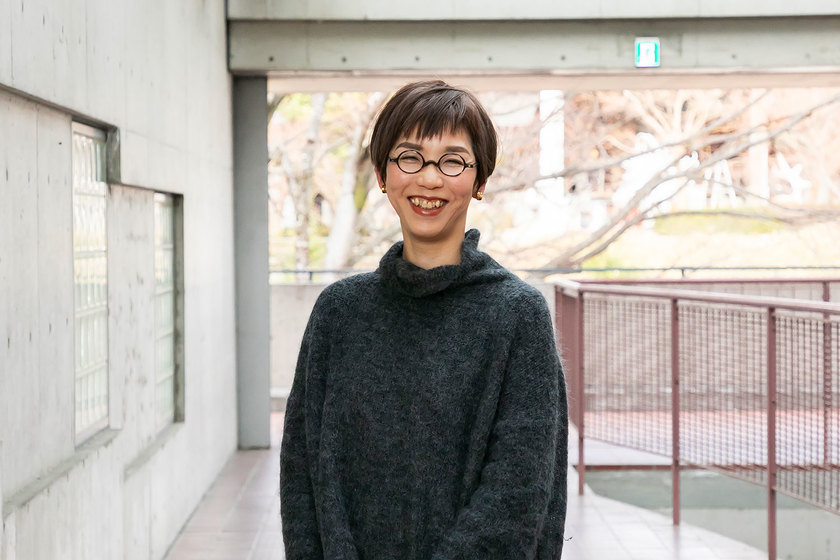
こんな先生・教授から学べます
日本の文化と歴史的建物が持つ価値を次代に繋ぐ先生
私たちのまわりに存在する、解体の危機を乗り越え継承されてきた建物や、惜しまれつつも失われてしまった建物の価値を明らかにし、文化として次代に繋ぐための歴史研究を専門としています。
建物は、何らかの目的や用途に基づき建てられています。構造体としてはまだまだ使えるにもかかわらず、その用途が今の時代と合わなくなったり、経済的ではないという理由から壊される建物も多くあります。一旦失われた建物の再現は容易なことではありませんし、先人が試行錯誤して完成させた当時の技法は解明されずに途絶えてしまうかもしれません。そうならないように、建物に積み重ねられてきたストーリーにも目を向け、多角的なアプローチをもった調査、研究を実践しています。そのうえで適切な保全の方法を考え、今の社会に応じた新しい活用の提案も行います。

古建築の調査研究では様々な道具を使い建物を実測したり、部材に残る痕跡や古記録なども丹念に収集します。
社会に対して、自分の提案が持つ「意味」を深く意識すること
小出先生は、学生が自ら建築を構想し、設計からプレゼンまでを行う「建築設計実習」も担当しています。学生の指導にあたり重視することや授業の雰囲気についてうかがいました。
「何かを新たに生み出すということは、大きな責任を伴います。自分の提案が社会にとってどんな意味があるのかを考え続けることを望みます。学生はキャンパスで出会う様々な分野の芸術から刺激を受けつつ制作に励み、その作品は学外のコンペなどでも高い評価を得ています」
建築を通じていかに社会に貢献できるのか。その問いに向き合い、日々課題に取り組みます。

日本の伝統建築について学ぶ授業も担当。さまざまな観点から建築を考える力を養います。
さまざまな芸術に触れながら建築を学べる場が、ここにあります
大阪芸大は15の学科が集まる総合芸術大学です。さまざまな芸術に触れられる環境は、建築を学ぶ上で大きな刺激になると思います。建築の領域は想像以上に幅広く、多様な芸術と出会うことで可能性を広げてくれます。

小出 祐子先生
専門分野は日本建築史。各地に残る近世~近代の建造物・建造物群の調査に関わり、それらの歴史遺産としての評価と保全活動を行っている。また、自らの研究テーマとして江戸期の幕府緊縮財政下において巨費を要した寺社の造営事業や、財政基盤確立のための方策が建築及び都市空間の形成に与えた影響の解明に取り組む。著書(共著)に『茶室露地大事典』(淡交社、2018) 、『カラー版図説 日本建築の歴史』(学芸出版社、2020)など。
※この画面の情報は、すべて取材した時点でのものになります。
この学校のおすすめ記事
-
 先生・教授1つのりんごから「気づきに気づく」デザインを伝える先生芸術学部デザイン学科 三木 健先生
先生・教授1つのりんごから「気づきに気づく」デザインを伝える先生芸術学部デザイン学科 三木 健先生 -
 在校生さまざまな観点から建築を学び、自分の殻をやぶる挑戦ができました建築学科
在校生さまざまな観点から建築を学び、自分の殻をやぶる挑戦ができました建築学科 -
 先生・教授人が持つ感覚のメカニズムを探求する先生芸術学部アートサイエンス学科 安藤 英由樹先生
先生・教授人が持つ感覚のメカニズムを探求する先生芸術学部アートサイエンス学科 安藤 英由樹先生 -
 先生・教授アナウンサーに必要な力と、可能性を広げる力を養う先生芸術学部放送学科 馬場 典子先生
先生・教授アナウンサーに必要な力と、可能性を広げる力を養う先生芸術学部放送学科 馬場 典子先生
