- スタディサプリ 進路(大学・専門学校)
- 大学・短大を探す
- 私立大学
- 新潟
- 新潟医療福祉大学
- 卒業後のキャリア一覧
- 松尾 宣英さん(心理・福祉学部 社会福祉学科/児童指導員)
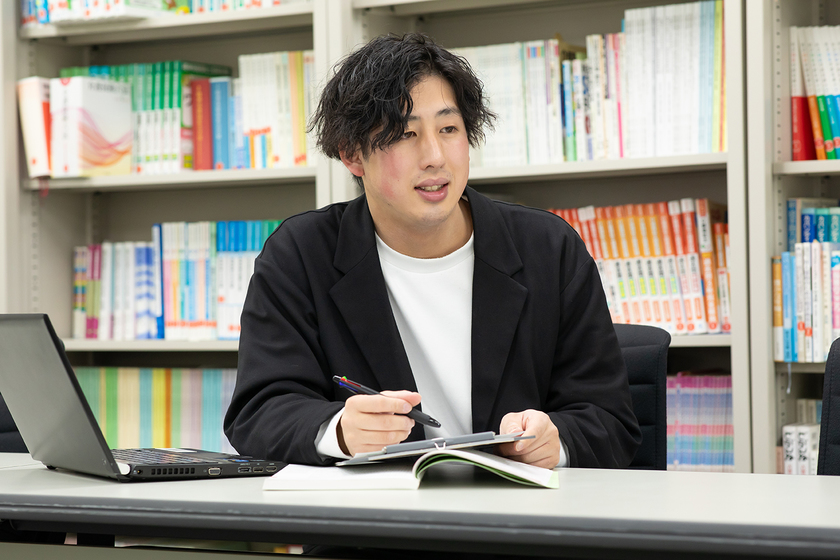
児童と共に自分も成長していける仕事です
先輩の仕事紹介
児童一人ひとりが自分の「将来像」や「夢」を思い描けるように支援しています
この仕事や研究の魅力・やりがい
児童指導員として、様々な理由で施設に入所している児童の学習支援や生活支援、関係機関との連携を行っています。児童に対して、一つのチームとして支援していくことが大切であり、職員間でコミュニケーションをとることでよりよい支援に繋がります。日頃から業務内容だけでなくプライベートなことなどでも積極的なコミュニケーションを意識して、どんな時でも、誰とでも連携して対応ができるように意識しています。感情の表現方法がまだ拙い児童に対して根気強く向き合ったことで正しい方法や言葉で表現してくれるようになったりと、児童の成長を感じられたときにはこの仕事のやりがいを感じます。
学校で学んだこと・学生時代
国家試験の合格率と就職率の高さ、充実した現場実習があることが魅力で新潟医療福祉大学に入学しました。在学中にも印象に残っているのは施設実習で、座学では学べないことを肌で体感することができるため、疑問に思ったことは積極的に質問して知識が増えるよう努めました。現在の職種に興味を持ったのも社会福祉士実習で児童養護施設で実習を行ったことがきっかけです。支援のやり方や児童への対応ひとつをとっても様々な意味や目的があることに驚き、魅力的な仕事だと感じました。先生方はみんな大変親身に接してくださり、特にゼミの先生は国家試験、就職活動とストレスのかかる中で親身に相談になってくれたことが励みになりました。
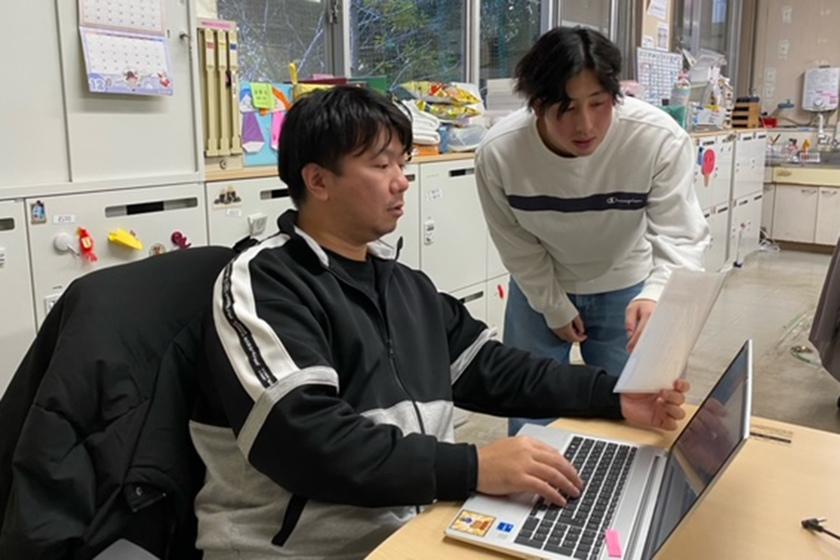
職員間のコミュニケーションを大切にしています
分野選びの視点・アドバイス
福祉施設ではチームによる支援が大切であるため、誰とでもコミュニケーションが取れる人は特に働きやすいと思います。私は学生時代、ボランティアの部活に所属していました。活動を共にする外部の人たちとの連携や調整といった機会を通じてコミュニケーション能力を育むことができたことが現在の仕事に活かされていると感じます。学生時代には、遊ぶときは遊ぶ、学ぶときは学ぶと、メリハリをつけて活動していくことが大事だと思います。施設実習は得られる経験が多いだけに心身ともに疲れてしまいますが、休日に思いっきり遊ぶことでリフレッシュして「また明日からも頑張ろう!」という気持ちを持つことができました。

児童の自主性を育むことを意識して関わっています

松尾 宣英さん
社会福祉法人愛宕福祉会 児童養護施設新潟県若草寮/社会福祉学部※ 社会福祉学科(※2024年4月から心理・福祉学部)/2021年卒/新潟県出身。児童との関わり方について気をつけていることは、「児童の自主性を育むような取り組みを行っていきたい。そのために、正解をすぐに教えるのではなく、ヒントを出しながら一緒に考えていくスタンスで関わるように意識しています」とのこと。
※この画面の情報は、すべて取材した時点でのものになります。
この学校のおすすめ記事
-
 在校生学業とサークル活動に打ち込み、大学生活での成長を実感しています!看護学部 看護学科
在校生学業とサークル活動に打ち込み、大学生活での成長を実感しています!看護学部 看護学科 -
 卒業後患者さんの「想い」に合わせたリハビリを提供できることが、この仕事の魅力ですリハビリテーション学部 作業療法学科 卒 作業療法士
卒業後患者さんの「想い」に合わせたリハビリを提供できることが、この仕事の魅力ですリハビリテーション学部 作業療法学科 卒 作業療法士 -
 卒業後視能訓練士とチアリーダーの「二刀流」で、笑顔を届けています医療技術学部 視機能科学科 視能訓練士
卒業後視能訓練士とチアリーダーの「二刀流」で、笑顔を届けています医療技術学部 視機能科学科 視能訓練士 -
 卒業後症例を見て検査を重ねるごとに、成長を実感できる仕事です医療技術学部 臨床技術学科 卒 臨床検査技師
卒業後症例を見て検査を重ねるごとに、成長を実感できる仕事です医療技術学部 臨床技術学科 卒 臨床検査技師
