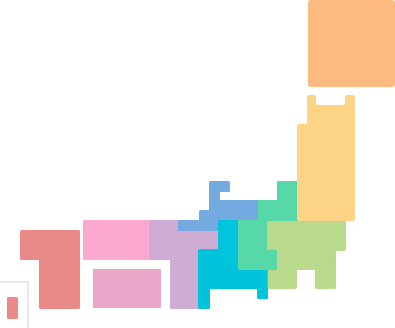クロマグロをはじめとする水産資源の養殖技術の開発や、品種改良などに取り組む
世界初のクロマグロの完全養殖に成功
マグロ、なかでもクロマグロは日本人にとって身近な食べ物ですが、太平洋のクロマグロは絶滅危惧種に認定されるなど、その数は年々減少しています。日本人の食生活が、生態系に危機をもたらしているのです。日本を含め、各国の政府は漁獲量に制限を設けるなどして対応していますが、それは私たちの食生活を大きく変えることになります。そこで、需要に合わせた安定供給のために多くの研究者が取り組んできたのが養殖。クロマグロをはじめ、日本のほとんど全ての養殖種を対象に養殖技術の開発に取り組む近畿大学の水産増殖学研究室では、長年クロマグロの養殖を研究に取り組み、2002年に世界初となる完全養殖に成功しました。完全養殖とは、養殖した魚が成魚となり、それが親となって、産卵、そこから孵化してまたそれが親となりといった、いわゆる天然の魚に頼らずに持続的な養殖を行うことです。この完全養殖の技術が確立され、安定供給ができるようになれば、私たちは食生活を変える必要がなくなります。そして、クロマグロと、それを取り巻く生態系も守ることができるのです。
現在、完全養殖に成功したものの、孵化から1カ月ほどで9割が死んでしまうなど、まだまだ課題は山積みです。こうした数々の課題の解決を目指し、日夜研究をしています。
品種改良でより安定した供給を
魚などの水産資源は、長い間海から獲ってくるのが当たり前でした。しかし、現代では、スーパーにいけば天然ものと養殖ものが同じくらい並んでいます。それだけ養殖技術が発達した証と言ってもいいでしょう。そして、それによって可能となってきたのが、水産資源の品種改良です。これまで、農作物や畜産物に関してはさまざまな品種改良が行われてきましたが、それは畑や牧場、厩舎などの限られた範囲で育てられていたからです。もし自然界で品種改良をしたら、そこの生態系はたちまち崩れてしまうことになります。当然、海の中でも同じです。しかし、水産資源を生簀や水槽で育てることができるようになった今、これらの生き物も、農作物や畜産物と同じように、生態系に影響を与えることなく品種改良できる環境になってきたというわけです。品種改良を重ねて、病気に強いものや成長の早いものを作れればそれだけ供給は安定しますし、トロばかりのクロマグロなんていうものも生み出せるかもしれません。その可能性を探って、遺伝子レベルでの研究を進めているところです。
持続可能な食糧供給のプロセスを確立することで、人の食生活を守り、生態系も保護する。そんな意義ある研究です。
全国のオススメの学校
-
北海道立農業大学校(畑作園芸経営学科)専門学校 / 北海道
-
帯広畜産大学(畜産学部)国公立大学 / 北海道
-
九州大学(農学部)国公立大学 / 福岡
-
 東洋大学(生命科学部)東洋大学は、14学部を擁する総合大学です。哲学教育を基礎として、世界に通用する人財を育成します私立大学 / 東京・埼玉
東洋大学(生命科学部)東洋大学は、14学部を擁する総合大学です。哲学教育を基礎として、世界に通用する人財を育成します私立大学 / 東京・埼玉 -
 鯉淵学園農業栄養専門学校(アグリビジネス科)「食」はみんなを笑顔にします。「タネまきから食卓まで」を学ぶ本校は、新鮮で安心な農畜作物を生産・流通して届けるプロ、乳幼児から老人まで全ての人の健康を毎日おいしく支える食を提供するプロを育成します。専門学校 / 茨城
鯉淵学園農業栄養専門学校(アグリビジネス科)「食」はみんなを笑顔にします。「タネまきから食卓まで」を学ぶ本校は、新鮮で安心な農畜作物を生産・流通して届けるプロ、乳幼児から老人まで全ての人の健康を毎日おいしく支える食を提供するプロを育成します。専門学校 / 茨城 -
 玉川大学(農学部)「全人教育」を理念に、学生一人ひとりのもつ可能性を引き出し、夢の実現に挑戦する人材を育成。緑豊かなキャンパスには、教育・文・芸術・経営・観光・リベラルアーツ・農・工学部の様々な夢をもつ学生が集います。私立大学 / 東京
玉川大学(農学部)「全人教育」を理念に、学生一人ひとりのもつ可能性を引き出し、夢の実現に挑戦する人材を育成。緑豊かなキャンパスには、教育・文・芸術・経営・観光・リベラルアーツ・農・工学部の様々な夢をもつ学生が集います。私立大学 / 東京 -
信州大学(農学部)国公立大学 / 長野
-
 龍谷大学(農学部)龍谷大学は、1639年に建学した京都、滋賀にある、10学部を擁する総合大学です。「自省利他」を行動哲学として、地球規模で広がる課題に立ち向かい、社会の新しい可能性の追求に力を尽くしていきます。私立大学 / 京都・滋賀
龍谷大学(農学部)龍谷大学は、1639年に建学した京都、滋賀にある、10学部を擁する総合大学です。「自省利他」を行動哲学として、地球規模で広がる課題に立ち向かい、社会の新しい可能性の追求に力を尽くしていきます。私立大学 / 京都・滋賀 -
 千葉科学大学(動物危機管理学科)薬学部、危機管理学部、看護学部の3学部を設置。危機管理の素養を身に付け、「健康で安全・安心な社会の構築」に寄与し、薬学・医療や航空・工学・動物・看護の各方面から暮らしの安全を守る人材を養成します。私立大学 / 千葉
千葉科学大学(動物危機管理学科)薬学部、危機管理学部、看護学部の3学部を設置。危機管理の素養を身に付け、「健康で安全・安心な社会の構築」に寄与し、薬学・医療や航空・工学・動物・看護の各方面から暮らしの安全を守る人材を養成します。私立大学 / 千葉 -
滋賀県立農業大学校(園芸課程)専門学校 / 滋賀
農学とはどんな学問?
農学とはどんな学問?
農学と他の学問とのかかわり
農学では何をどのように学ぶか
農学はこんな人に向いている
農学を学んだ後の進路と今後の展望
農学の先生に聞く
農学ではこんな研究をしています
農学のここが面白い
もっと先生たちに聞いてみよう

さまざまな再生可能エネルギーの活用法を教えてくれる先生
酪農学園大学 農食環境学群農環境情報学類
石川 志保先生
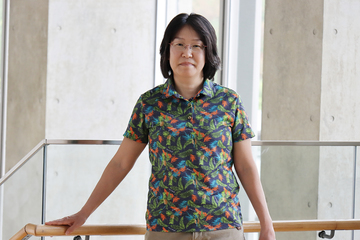
お米の澱粉を研究し、加工品の販売普及まで行っている先生
秋田県立大学 生物資源科学部生物生産科学科
藤田 直子教授

有機農業を通じて食と地域を“根っこ”から見直す先生先生
明治国際医療大学 農学部
秋津 元輝先生
農学の学生に聞く
もっと在校生たちに聞いてみよう

目標は野菜生産の現場で祖父のような熟練の技術者になること
テクノ・ホルティ園芸専門学校 野菜生産コース
島村 拓実さん

夢は農業法人の立ち上げ!大規模で効率的なスマート農業に挑戦!
東北農林専門職大学 農林業経営学部・農業経営学科
山田 開晴さん

花は生活や人生の節目を彩る大切な存在。その魅力を伝えていきたい!
テクノ・ホルティ園芸専門学校 花き生産コース
N.M.さん
もっと卒業生たちに聞いてみよう

自分の経験を基に、花の魅力や育て方、管理方法をたくさんの人に伝えていきたい
テクノ・ホルティ園芸専門学校
花き生産コース

学生時代、野菜づくりの授業を通して野菜の味に感動!そしてこの道を志しました。
テクノ・ホルティ園芸専門学校
園芸療法・福祉コース(2019年4月 野菜生産コースに名称変更)

技術と感性。その両方を磨くことが良い庭園を生み出す秘訣です。
テクノ・ホルティ園芸専門学校
造園コース