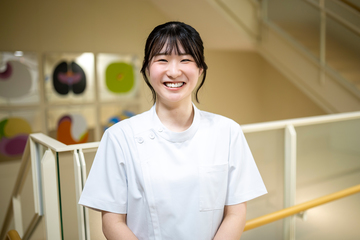- スタディサプリ 進路(大学・専門学校)
- 専門学校を探す
- 専門学校
- 岡山
- 専門学校川崎リハビリテーション学院
- 在校生レポート一覧
- 杉 幾久さん(作業療法学科/2年生)

キャンパスライフレポート
患者さんの強みに着目し「できる!」を増やせる作業療法士に
作業療法学科 2年生
杉 幾久さん
- 岡山県 岡山後楽館高等学校 卒
私のキャンパスライフShot!
-

患者さんの状態を把握し、リハビリを計画
-

実践を通じて、作業に必要な身体機能を理解
-
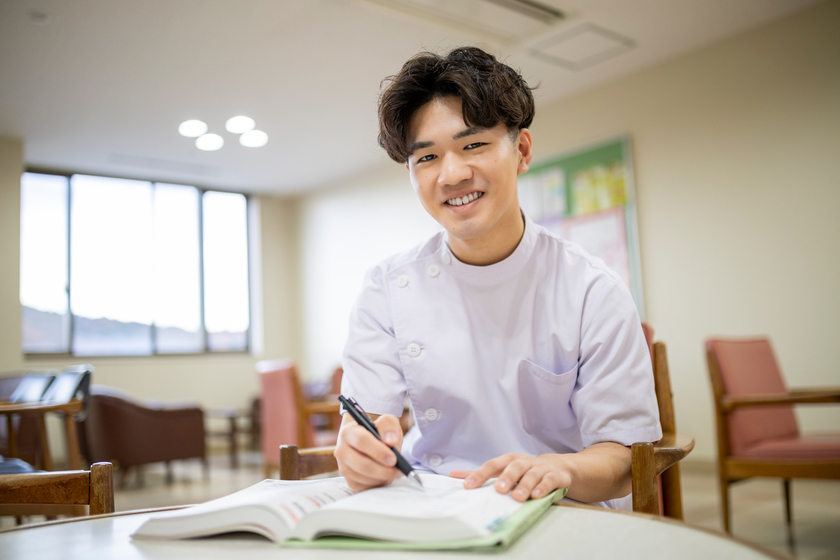
臨床実習後は内容を振り返りレポートを作成
学校で学んでいること・学生生活
2年次以降の臨床実習は実際の患者さんと接して行うため、緊張感や責任もより大きなものとなります。その分喜びや達成感も大きく、医師による治療やリハビリテーションを通して機能回復の兆しが見えた患者さんが感激する姿を見た時は、やりがいを強く実感するとともに作業療法の在り方についても考える機会となりました。
これから叶えたい夢・目標
身体面・精神面など患者さんの強みや環境にも着目し、身体機能の回復や日常生活への復帰に活かすことのできる作業療法士が目標です。まずは患者さんのご家族に理解をいただけるように難しい言葉を使わず疾患などを説明できるように。社会福祉の知識も深め、患者さんと社会的サービスの橋渡しを行える存在になりたいです。
この分野・学校を選んだ理由
高校で介護福祉を学んだことから医療に関する仕事を志望していました。本学院への入学の決め手はリハビリテーションセンターに併設された環境です。医療の厳しさや緊張感に触れながら学べることに魅力を感じました。
分野選びの視点・アドバイス
臨床に直結した環境で早期から実習に取り組める環境は職業理解につながり、学修意欲も高まると感じています。また3年制で学ぶことにより早く現場経験を積めることや、メリハリのついた学生生活を送れると思います。
1週間のタイムスケジュール
| 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1限目 | 公衆衛生学 | 整形外科学II | 身体障害治療学IV テスト | 解剖学実習II | ||
| 2限目 | 身体障害治療学VI | 身体障害治療学IV テスト | 解剖学実習II | |||
| 3限目 | 身体障害治療学VI | 技術論実習 | 臨床実習II | |||
| 4限目 | 身体障害治療学VI | 技術論実習 | 病理学 期末テスト | 臨床実習II | ||
| 5限目 | リハビリテーション医学II | 身体障害治療学V | 運動学実習 | 運動学実習 | ||
| 6限目 | 身体障害治療学V | 運動学実習 | 運動学実習 | |||
| 7限目 | 臨床実習II | 技術論実習 | 臨床実習II | |||
| 8限目 | 臨床実習II | 技術論実習 | 臨床実習II |
医療の学びは基礎からの積み上げが重要です。1年次で学んだ「基礎作業学実習」などで動作分析を行うことは楽しくもあり、臨床でも基盤となる知識。複数の科目のつながりを意識しながら学ぶことで理解も深まります。
※この画面の情報は、すべて取材した時点でのものになります。
この先輩が通っているのは...