- スタディサプリ 進路(大学・専門学校)
- 専門学校を探す
- 専門学校
- 岡山
- 専門学校倉敷リハビリテーション学院
- 先生・教授一覧
- 藤田 隆之先生(理学療法士)

こんな先生・教授から学べます
他業種から医療職へ。人の役に立てるやりがいを伝える先生
理学療法士が患者さんの身体機能を正確に評価するには、筋肉や関節、神経の構造と機能的な働きを理解する必要があります。その基盤となる学問が「機能解剖学」。身体の構造である骨・筋・神経などの解剖学的知識と、それらがどのように機能し動作に関わるかについて生理的・運動学的な側面を統合して学ぶ分野であり、患者さん一人ひとりの状態に応じた運動療法や介入方法を立案するにあたり「なぜこの運動を行うのか」「どの筋肉を強化・伸張するべきか」という根拠に基づくリハビリテーションを計画し、効果の高い理学療法の実現のために不可欠な知識です。また、理学療法は医師や看護師、作業療法士などの多職種連携のもと行われます。機能解剖学は共通の専門知識として重要な役割を果たし、円滑な連携やチーム医療の質の向上にも重要なものなのです。
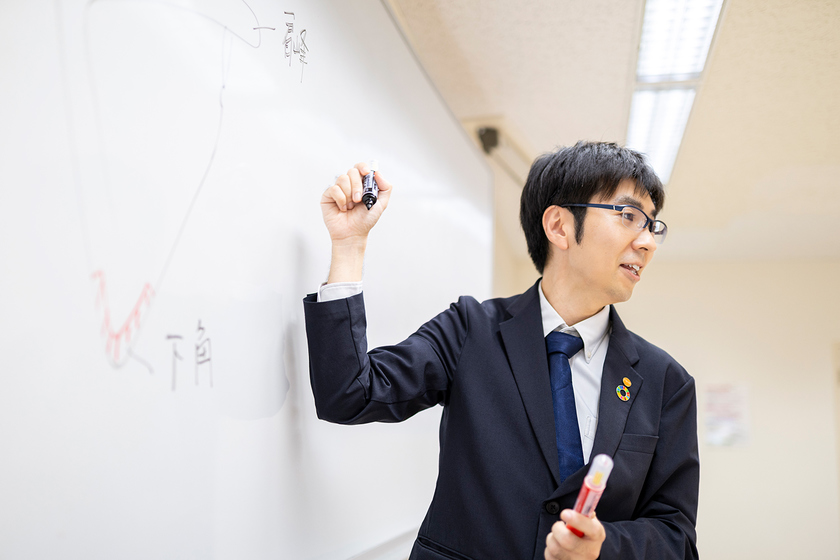
機能解剖学の知識は患者さんへの説明や指導においても不可欠。適切な理解がモチベーションの向上につながる
身体の構造を三次元的に理解し、解剖と機能障害のイメージを結び付ける体験型の授業を展開する
機能解剖学は、身体構造と機能を理解するための基盤である一方で、実際の解剖と機能障害のイメージを結び付けにくく、理解が難しいという難点があります。授業を行う中で、藤田先生が心がけているのは体験による実感。骨や筋肉の模型を用いて三次元的に解剖構造の理解を深め、さらに学生同士で身体に触れながら学ぶことにより筋肉の触診や関節の可動域の確認、日常動作の中での筋の動きを観察するといった体験型授業を実施しています。体験型の授業を通して、コミュニケーションや臨床場面での接遇姿勢の基礎作りにもつなげています。

思考力を養うため「この関節が硬くなると日常生活動作にどんな支障が出る?」などの問いを投げかけることも
スタートラインは同じ。仲間と支え合いながら成長していける環境があります
本学には多様な学科を卒業した学生が入学しています。もしも今、人の役に立てる仕事や医療に興味があるならその気持ちをぜひ大切にしてください。踏み出す一歩が、きっとあなたの未来を変えるきっかけになりますよ。

前職は接客業。理学療法士という仕事を知り、人の役に立てることの喜び、やりがいに魅了されたという
藤田 隆之先生
専門分野/解剖学I、保健体育、リハビリテーション医学、基礎機能解剖学、日常生活活動学、地域理学療法学演習
略歴/社会人入学にて専門学校倉敷リハビリテーション学院で学びを修め、2018年3月卒業。就職後は機能訓練指導員として勤務した。2023年7月より現職。後進の指導に熱意を注ぐ。
※この画面の情報は、すべて取材した時点でのものになります。


