- スタディサプリ 進路(大学・専門学校)
- 大学・短大を探す
- 私立大学
- 愛知
- 名古屋学芸大学
- 卒業後のキャリア一覧
- 山田 希生さん(ヒューマンケア学部 子どもケア学科子どもケア専攻<養護教諭>/養護教諭)

子どもたちがどんなことでも相談できる先生でありたい。
先輩の仕事紹介
子どもの気持ちに寄り添い、自立心を育む養護教諭をめざしています。
この仕事や研究の魅力・やりがい
養護教諭である私の一日は、毎朝子どもたちを迎えることから始まります。表情や様子を観察し、少しの変化も見逃さないよう見守ります。その後も水質検査や保健だよりの作成、保健教育などの職務にあたり、保健室への来室があれば随時ケアを行います。その際、ケガや病気の状態を確認することはもちろん大切ですが、ケガの場合なら「痛かったね」と声を掛けて安心させたり、腹痛や頭痛の場合は背景に悩みや生活の乱れがないか、丁寧に話を聞いたりするなど、子どもの気持ちに寄り添う姿勢も大切にしています。ケガや病気から回復し、子どもたちが元気になった姿を見せに来てくれるのは何よりうれしく、日々の励みになっています。
学校で学んだこと・学生時代
アセスメントや応急処置法、カウンセリング技法、発達段階に応じた保健指導のスキルなど、養護教諭の仕事に直結する知識とスキルを広く学びました。なかでも印象的なのは、スクールソーシャルワーカーの先生の授業で、「自立している人=SOSを出せる人」と教わったこと。この学びから、子どもたちに何もかもをやってあげるのではなく、子どもたち自身が助けを求められるようにサポートしたいという養護教諭観が定まりました。現在も、ケガ・病気を問わず状態が深刻でなければ、頑張って教室に戻るか、保健室で休むかの判断を子どもに委ね、自分自身で考え、言葉にして伝える力を育むよう意識しています。

書類や保健だよりの作成などパソコン業務も多いです。
この分野・仕事を選んだきっかけ
高校生の頃、悩みのあった私の話を親身になって聞いてくれた養護教諭に憧れ、その先生の母校でもある名古屋学芸大学に入学しました。同じ目標を持つ仲間と切磋琢磨しながら勉強した時間は本当に楽しく、充実していました。私が採用試験への挑戦を諦めかけた時、「一緒に頑張ろうよ」と支えてくれた友人の言葉は今も忘れられません。また教員採用試験に向けた先生方の熱心であたたかな対策講座や面接指導のおかげで、本番の面接でも落ち着くことができ、自信を持って自分をアピールすることができました。高校時代に私を支えてくれた養護教諭、そして夢を実現させてくれた名古屋学芸大学には、感謝の気持ちで一杯です。

処置中は子どもを安心させる声掛けも意識しています。

山田 希生さん
愛知県 公立小学校 勤務/ヒューマンケア学部 子どもケア学科 子どもケア専攻<養護教諭>/2021年3月卒/保健室での対応と同様に、山田さんが重視するのは保健指導。健康診断の時などに行うミニ講義に加え、45分間の保健の授業を任されることもあるそう。「感染症が流行っている時期は、低学年にはバイ菌のイラストを使って視覚的にわかりやすく伝え、高学年には数字やグラフで説得力を持たせるなど、同じテーマでも年齢に応じて授業を組み立てています」と語る。授業では、保健室とは違う子どもたちの真剣に学ぶ姿を見ることもでき、子ども一人ひとりをより多面的に理解することができるのだそう。
※この画面の情報は、すべて取材した時点でのものになります。
この学校のおすすめ記事
-
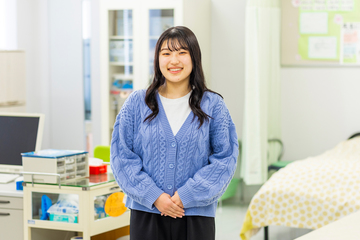 在校生一人ひとりに寄り添い、安心感を与えられる養護教諭になりたいヒューマンケア学部 子どもケア学科 子どもケア専攻<養護教諭>
在校生一人ひとりに寄り添い、安心感を与えられる養護教諭になりたいヒューマンケア学部 子どもケア学科 子どもケア専攻<養護教諭> -
 卒業後患者さんの心身の苦痛を和らげ、回復まで支え続ける伴走者でありたい。看護学部 看護学科 看護師
卒業後患者さんの心身の苦痛を和らげ、回復まで支え続ける伴走者でありたい。看護学部 看護学科 看護師 -
 卒業後みんなの気持ちに寄り添いながら、子どもと保育士が安心して過ごせる園をつくりたい。ヒューマンケア学部 子どもケア学科 幼児保育専攻 保育士(主査)
卒業後みんなの気持ちに寄り添いながら、子どもと保育士が安心して過ごせる園をつくりたい。ヒューマンケア学部 子どもケア学科 幼児保育専攻 保育士(主査) -
 在校生小児科の看護師として、病気と闘う子どもたちに寄り添える看護をしたい看護学部 看護学科
在校生小児科の看護師として、病気と闘う子どもたちに寄り添える看護をしたい看護学部 看護学科
