
キャンパスライフレポート
小児科の看護師として、病気と闘う子どもたちに寄り添える看護をしたい
看護学部 看護学科 2年
鈴木 花菜さん
- 愛知県 熱田高等学校 卒
私のキャンパスライフShot!
-

2年次からは、アセスメントや注射、点滴など、より実践的なスキルを学びます
-

小児や母性、老年など各領域ごとに実習室があり、様々な看護を実践的に学べます
-

名古屋医療センター開催のイベント「金シャチフェスタ」でレモネードを販売。売上は愛知こどもホスピスへ
学校で学んでいること・学生生活
小児ボランティアサークルの部長をしています。子どもホスピスの勉強会で立ち上げの話が出て、自分も何かできればと参加。病気や障がいのある子どもたちと交流したり、レモネードスタンドを出店し募金活動を行ったりしています。やりたいことと社会が求めることが合致すれば、ボランティアにつながることを実感しています。
これから叶えたい夢・目標
子どもとかかわることが好きで医療に興味があったことから、病気と闘う子どもたちを支援したいと思うようになりました。今後は闘病中の子どもたちだけでなく、そのきょうだい児の支援についての知識も深めたいと思っています。卒業後は小児科の看護師として、子どもたちに寄り添う看護をしたいと思います。
この分野・学校を選んだ理由
実習先が名古屋医療センターをはじめ、国立病院機構の病院が中心であることに大きな魅力を感じました。先生との距離が近くて楽しい雰囲気で、不安なことをすぐに相談できそうな環境にも惹かれました。
分野選びの視点・アドバイス
名古屋医療センターや豊橋医療センターなど、国立病院機構の病院に就職した先輩が多く、目標になります。また、サークルや行事は多くの人との協働が必要になるため、医療で重要なチーム力が自然に身につきます。
1週間のタイムスケジュール
| 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1限目 | 生涯発達論 | ヘルスアセスメント | 診断治療学概論 | |||
| 2限目 | 障害と看護 | ヘルスアセスメント | 精神看護学概論 | |||
| 3限目 | 保健行動論 | 病態治療学1 | ヘルスアセスメント | 母性看護学概論 | ||
| 4限目 | 病態治療学4 | 病態治療学5 | 病態治療学2 | 病態治療学3 | ||
| 5限目 | ||||||
| 6限目 |
「障害と看護」では、難病のハンディキャップを抱える作業療法士の方から、障がいについて当事者と作業療法士の立場で話を聞くことができ、看護師にできる障がい者支援について学ぶことができました
※この画面の情報は、すべて取材した時点でのものになります。
この先輩が通っているのは...
この学校のおすすめ記事
-
 卒業後患者さんの心身の苦痛を和らげ、回復まで支え続ける伴走者でありたい。看護学部 看護学科 看護師
卒業後患者さんの心身の苦痛を和らげ、回復まで支え続ける伴走者でありたい。看護学部 看護学科 看護師 -
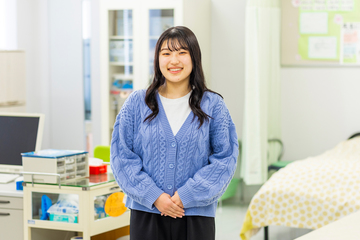 在校生一人ひとりに寄り添い、安心感を与えられる養護教諭になりたいヒューマンケア学部 子どもケア学科 子どもケア専攻<養護教諭>
在校生一人ひとりに寄り添い、安心感を与えられる養護教諭になりたいヒューマンケア学部 子どもケア学科 子どもケア専攻<養護教諭> -
 卒業後WEBサイトやSNSの企画を通して、ブランドや商品の魅力を発信しています。メディア造形学部 ファッション造形学科 販売促進・WEBマーケティング
卒業後WEBサイトやSNSの企画を通して、ブランドや商品の魅力を発信しています。メディア造形学部 ファッション造形学科 販売促進・WEBマーケティング -
 卒業後デザインのプロとして妥協することなく、人の心を動かす広告を生み出していきたい。メディア造形学部 デザイン学科 デザイナー/UIUXデザイナー職
卒業後デザインのプロとして妥協することなく、人の心を動かす広告を生み出していきたい。メディア造形学部 デザイン学科 デザイナー/UIUXデザイナー職
看護学科で目指せる仕事
