
こんな先生・教授から学べます
体験ファーストで知的好奇心を高めてくれる先生
解剖学実習では、全身の筋肉一つひとつを触診する技術の習得に加え、それらの筋肉に関係する疾患の評価方法や治療方法を学びます。評価するにあたり、触診の仕方を学ぶ前に筋肉の名称を覚えることが必要です。私は学生たちに教える際に、「体験ファースト」を意識しています。それは実際に体験することで、学問への知的好奇心を高めてほしいからです。また自分が経験してきた臨床の実践をできる限り伝えて、作業療法の楽しさを伝えたいと思っています。作業療法は病気を治す急性期に始まり、障がいを治す回復期、生活をサポートする生活期に移行していきますが、どの段階にも変化は起こり、それが患者さんの幸せにつながります。作業療法は、自分自身の人生を豊かにしてくれることも、伝えたいと思っています。

ストレッチポールを使うと、体のバランス力を知ることができる。
姿勢不良が生活習慣病に与える影響について研究を進める
パソコンやスマートフォンなどを使用する際、姿勢が悪くなっている人が少なくありません。日々過ごしている姿勢が運動器疾患や食事、運動、休養などが原因とされる生活習慣病にも関係している考えられています。私が「パソコン肘」と提唱している「上腕骨外側上顆炎」も、長時間にわたり不良姿勢でパソコンを使い続け、肩甲骨や関節の位置が悪くなることと仮説を立て、研究を進めているところです。良い姿勢を保てるよう体幹機能を高めることが病気や疾患の予防につながり、人生100年時代に向けた取り組みになることを期待しています。

ゼミに所属する学生と一緒に。卒業生が大学院に入学し、指導教員として再び関わることも多い。
ゲームでも料理でも音楽でも、何でも好きなことが作業療法につながる!
作業療法分野は、一人ひとりの好きが仕事になる領域です。それがゲームでも料理でも音楽でも好きなことは作業療法に活かされていきます。好きなことを通して、患者さんと自分の人生を豊かにしたい人を待っています。

大学での研究を臨床現場に還元し、そこでの経験を研究に生かす。「それが自分の使命」と話す金子先生
金子 翔拓教授
専門:解剖学、運動学、作業療法治療学等
千歳リハビリテーション学院卒業後に勤務した病院で臨床ハンドセラピィに興味を持ち、札幌医科大学大学院保健医療学博士課程に進学。「前腕肢位と手指屈曲伸展による手根管横断面積の変化」で作業療法学・博士号を取得。恵庭市内で「健康サロン」を展開し、平均寿命と健康寿命の差を小さくする方法の研究を進めることで地域住民の健康に寄与するほか、コミュニティの場を提供している
※この画面の情報は、すべて取材した時点でのものになります。
この学校のおすすめ記事
-
 先生・教授治療にも予防にも良いレッドコードを教えてくれる先生医療保健科学部リハビリテーション学科 大森 圭教授
先生・教授治療にも予防にも良いレッドコードを教えてくれる先生医療保健科学部リハビリテーション学科 大森 圭教授 -
 在校生作業療法士を目指して勉強したことを活かし、世の中に貢献したい!医療保健科学部 リハビリテーション学科 作業療法学専攻
在校生作業療法士を目指して勉強したことを活かし、世の中に貢献したい!医療保健科学部 リハビリテーション学科 作業療法学専攻 -
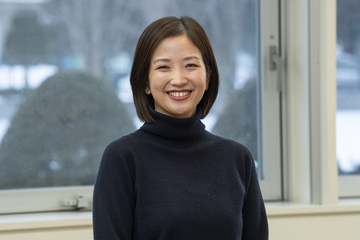 卒業後今後も自分のペースで自動車運転支援の研究を続け、将来は博士課程進学を目指したい人間科学部 作業療法学科(現:医療保健科学部 リハビリテーション学科 作業療法学専攻) 卒 作業療法士
卒業後今後も自分のペースで自動車運転支援の研究を続け、将来は博士課程進学を目指したい人間科学部 作業療法学科(現:医療保健科学部 リハビリテーション学科 作業療法学専攻) 卒 作業療法士 -
 卒業後フライトナースとなって救急救命の最前線で活躍する夢を叶え、日々精進しています!人間科学部 看護学科(現医療保健科学部 看護学科) 卒 看護師・フライトナース
卒業後フライトナースとなって救急救命の最前線で活躍する夢を叶え、日々精進しています!人間科学部 看護学科(現医療保健科学部 看護学科) 卒 看護師・フライトナース
