- スタディサプリ 進路(大学・専門学校)
- 大学・短大を探す
- 私立大学
- 北海道
- 北海道文教大学
- 卒業後のキャリア一覧
- 富田 遥香さん(医療保健科学部 リハビリテーション学科/作業療法士)
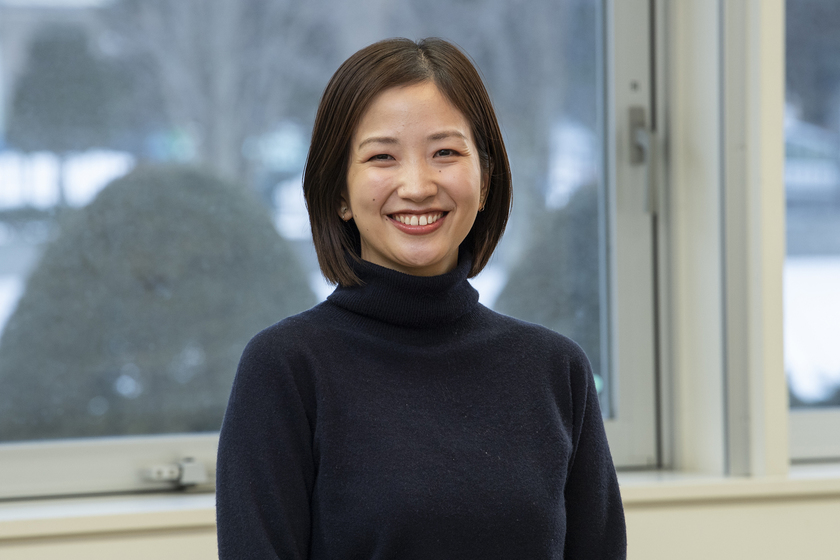
「研究テーマを追求するのは面白い」と話す富田さん
先輩の仕事紹介
今後も自分のペースで自動車運転支援の研究を続け、将来は博士課程進学を目指したい
この仕事や研究の魅力・やりがい
生活支援に関わる作業療法士の領域は幅広く、着替えや食事、入浴などの日常生活をはじめ、外を歩く買い物をするなど、患者さんに必要な動作の獲得に向けてリハビリテーションを行います。患者さんの状態やリハビリテーションの進め方も一人ひとり違うので、立ったり歩いたりの先に何をしたいのかをくみ取り、退院後の生活につなげていくことが大切です。担当した患者さんが自宅に戻った後もその人らしく生活に満足できる、あるいは同居するご家族が喜んでいる姿を見るたびに、この仕事についてよかったと思います。現在は育児休業中ですが、子育てした経験やその中で気づいたことを、育児中のママの支援に役立てていきたいです。
業界ココだけ話!
作業療法士は病院で働いて、目の前で困っている患者さんを支援する仕事ですが、その経験を活かして研究を行っている人も多いです。私も入職して2年目には、「脳卒中後の自動車運転再開支援」をテーマに研究を始め、学会で発表も行っていました。自分が気になることを追求するのが面白く、何事も考える習慣がついた気がします。研究成果を患者さんに還元し、役立てることができたらうれしいです。病院で働いていると理学療法士は体育会系、作業療法士はほんわか系と思うことが多いです。作業療法士は常に「どうしたら患者さんが楽しくいられるか」を考えながら働いているので、自分も幸せになれる仕事だからではないかと思っています。
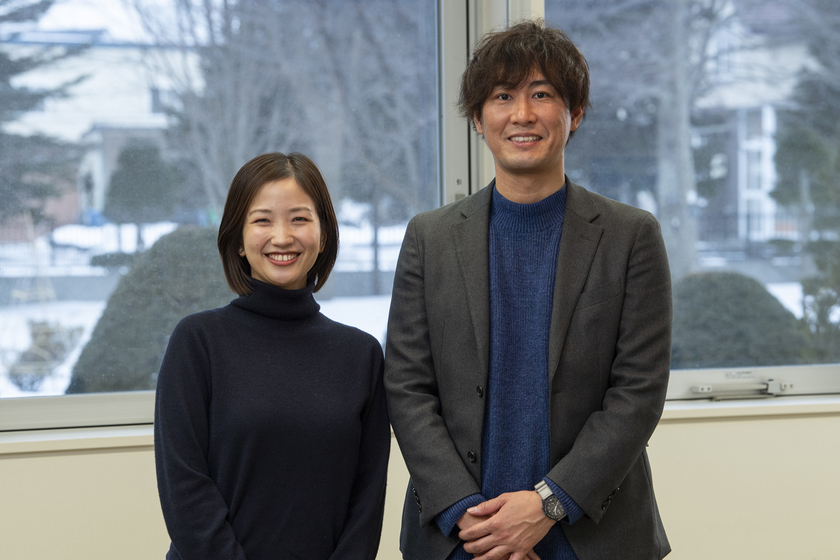
大学院の指導教員でもある、金子先生と一緒に
これからかなえたい夢・目標
自宅での生活や復職にあたって、車の運転をしたいと話す患者さんも少なくありません。しかし、自動車の運転は患者さんによって目的や環境が異なり、作業療法士として評価や支援をするのが難しい分野の一つでもあります。ケガや病気のために運転を諦める患者さんを減らすためには、適切な評価ができる作業療法士が必要です。大学院に進学したことで勤務する病院以外の研究に触れる機会が増え、考え方が広がり、ディスカッションもできるようになりました。今後も自分のペースで研究を続け、機会があれば博士課程に進学したいと考えています。母になったからこそ、カッコ良くいられるようにがんばっていきたいです。

さまざまな実習室を完備

富田 遥香さん
蒲田リハビリテーション病院勤務/人間科学部 作業療法学科(現:医療保健科学部 リハビリテーション学科 作業療法学専攻) 卒/2014年卒/大学卒業後は、回復期リハビリテーション領域の先駆けである船橋市立リハビリテーション病院に入職。8年間研鑽を積むなかで、自動車運転支援に興味を持つようになり、研究班に所属して研究発表を開始。2022年の大学院入学を機に、仕事と研究の両立が可能な現職へ。2024年夏に第一子を出産し、現在は育児休業中。
※この画面の情報は、すべて取材した時点でのものになります。
この学校のおすすめ記事
-
 先生・教授在学中に食品開発の面白さを体験させてくれる先生人間科学部健康栄養学科 山森 栄美准教授
先生・教授在学中に食品開発の面白さを体験させてくれる先生人間科学部健康栄養学科 山森 栄美准教授 -
 先生・教授体験ファーストで知的好奇心を高めてくれる先生医療保健科学部リハビリテーション学科 金子 翔拓教授
先生・教授体験ファーストで知的好奇心を高めてくれる先生医療保健科学部リハビリテーション学科 金子 翔拓教授 -
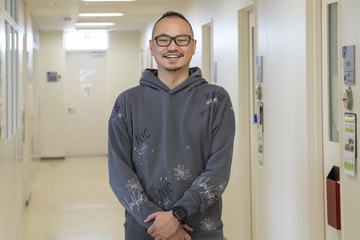 先生・教授学生の自主性を大切に、体験する機会を与えてくれる先生人間科学部こども発達学科 美馬 正和准教授
先生・教授学生の自主性を大切に、体験する機会を与えてくれる先生人間科学部こども発達学科 美馬 正和准教授 -
 在校生作業療法士を目指して勉強したことを活かし、世の中に貢献したい!医療保健科学部 リハビリテーション学科 作業療法学専攻
在校生作業療法士を目指して勉強したことを活かし、世の中に貢献したい!医療保健科学部 リハビリテーション学科 作業療法学専攻
