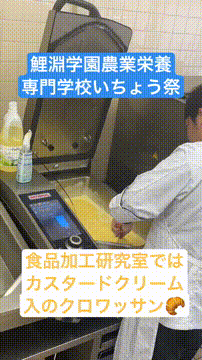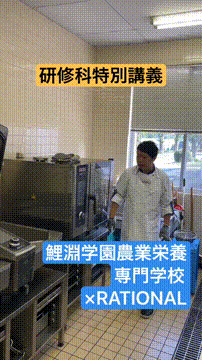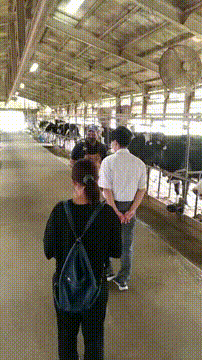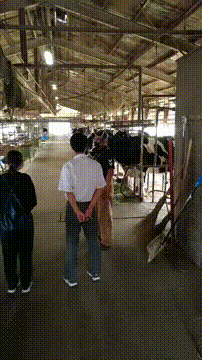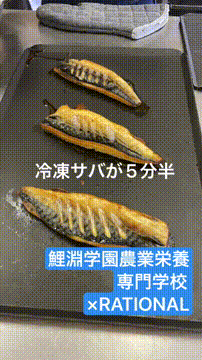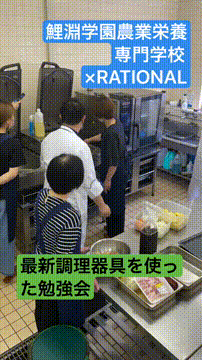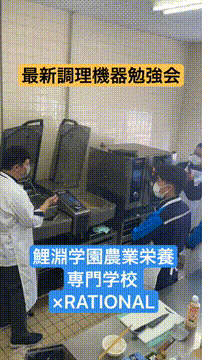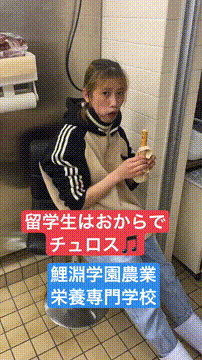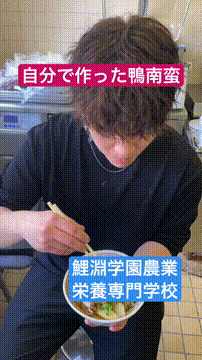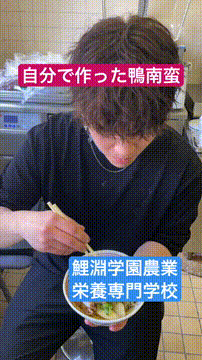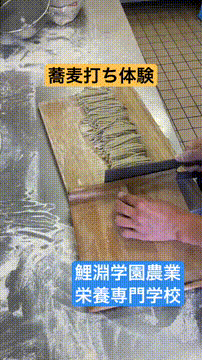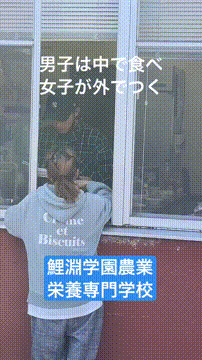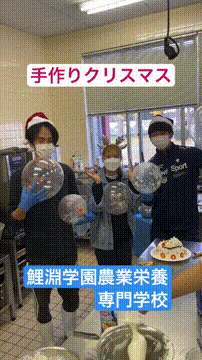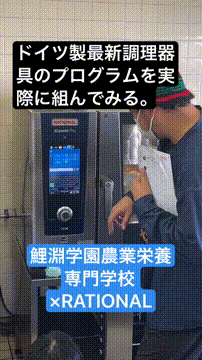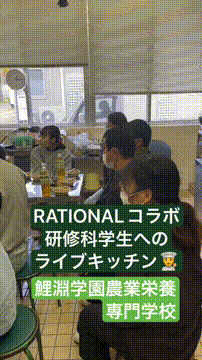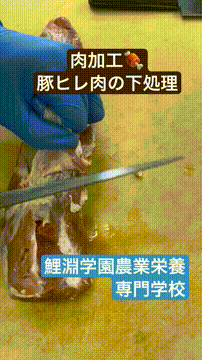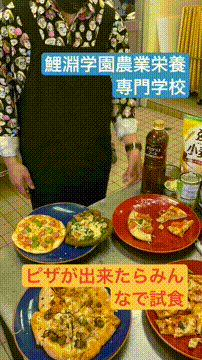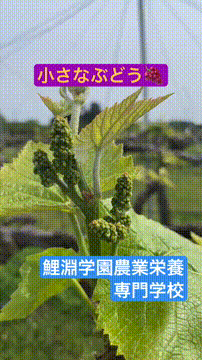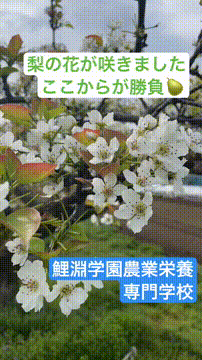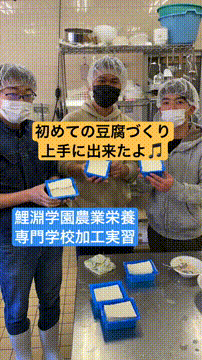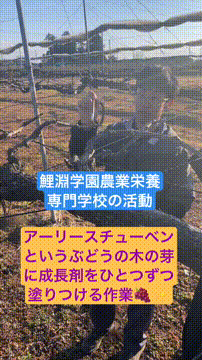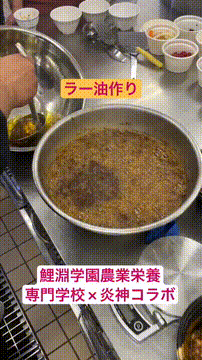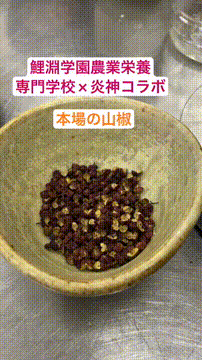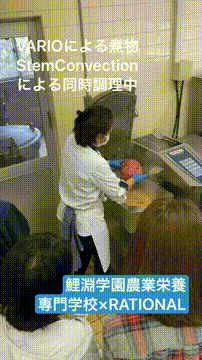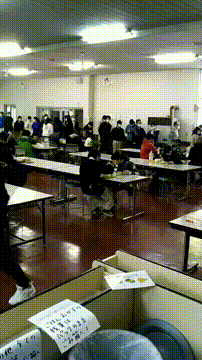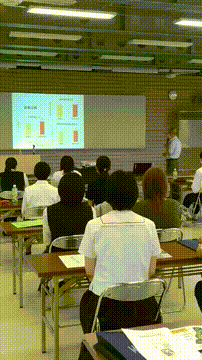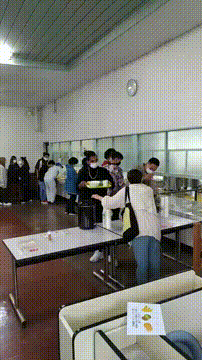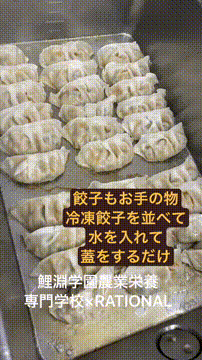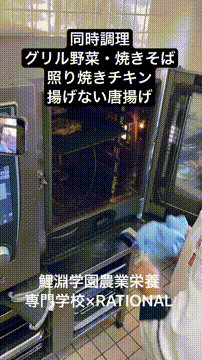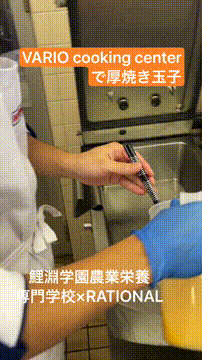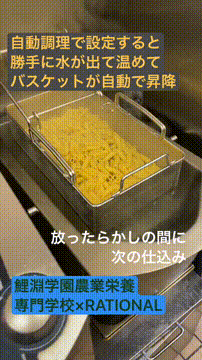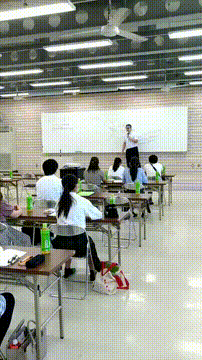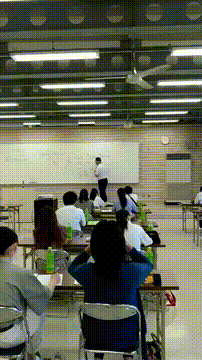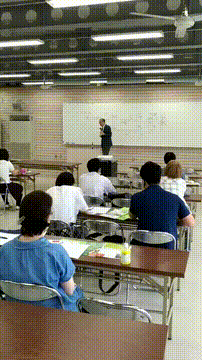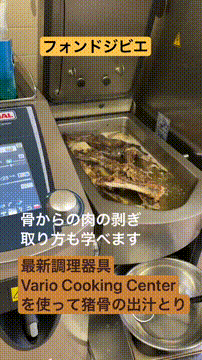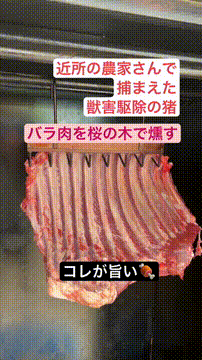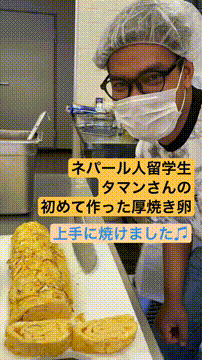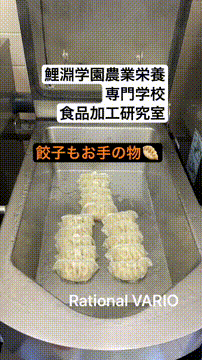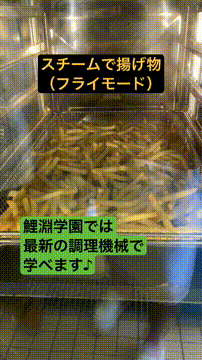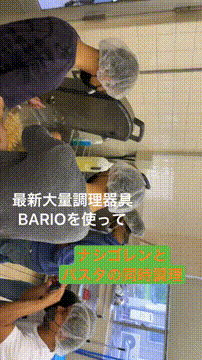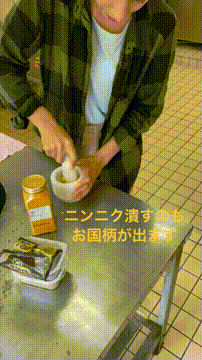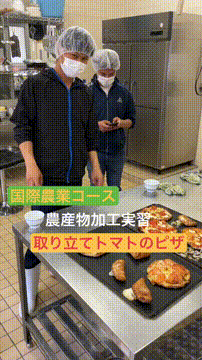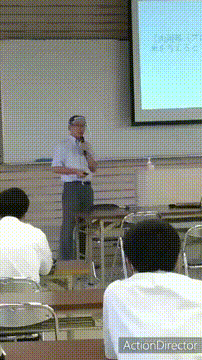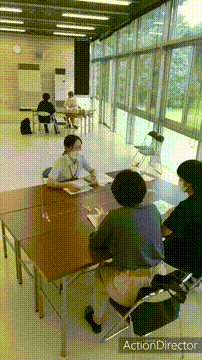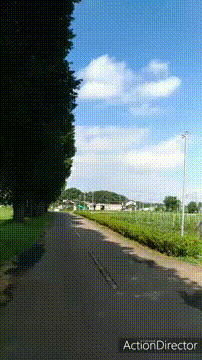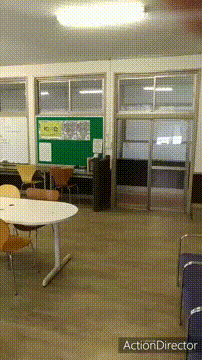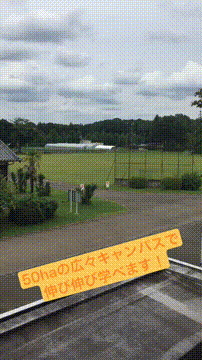鯉淵学園農業栄養専門学校 アグリビジネス科
- 定員数:
- 60人
自然の営みを知り、新たな農業をめざす人材を育成
| 学べる学問 |
|
|---|---|
| 目指せる仕事 |
|
| 初年度納入金: | 2025年度納入金(参考) 121万円 |
|---|---|
| 年限: | 2年制 |
鯉淵学園農業栄養専門学校 アグリビジネス科の学科の特長
アグリビジネス科の学ぶ内容
- 「環境との調和」と「古くて新しい技術」で価値や富を生み出す農業を
- 有機栽培認定農場があり、古くからの農業技術も活かしながら環境に調和した農業を実践しています。また、近年発達しているドローンなどアグリテックの導入や、付加価値を生み出す農産加工にも積極的に取り組んでいます。さらに、農業経営系の科目が充実しており、『つくる』だけでなく『かせげる』農業を学べます。
アグリビジネス科のカリキュラム
- 生産から販売までを意識した「校内インターンシップ」
- 農場実習で学生が育てた農作物は、市場・直売所・契約スーパーなどで全て販売しており、農産物直売所「農の詩」では販売現場に触れることもできます。また、学生が主体的に栽培した農作物を直売所で販売して収益を上げる「校内起業」も意欲的に実施。このような「校内インターンシップ」で実践力を常に養います。
アグリビジネス科の先生
- 環境にも配慮した生産技術を学びます(平澤 朋美 教授)
- 「生産性や環境との調和を意識して、地域の未利用資源の有効活用や堆肥を用いた土づくりを基本に、化学肥料・農薬を適正に使用することも含めた持続性の高い『環境保全・循環型農業』を学びます。資源豊かな農場の実習を通じ、作物・野菜・果樹などの栽培技術を基礎から学び、実践力を身につけましょう」
アグリビジネス科の教育目標
- 幅広い視点・知識を身につけて「アグリビジネス」で活躍できる人材を育成
- 農業生産者だけでなく、消費者も視野に入れた農産物加工/流通を身に付けることを目指しています。日本の農業・食料を取り巻く状況が変化していく中で、「農と食の連携」「スマート農業」「農業の多角的展開」「海外農産物市場への展開」など新たな挑戦が求められる農業ビジネスをリードしていける人材を育成します。
アグリビジネス科の制度
- 個人に合わせた就職・就農・進学サポート
- 入学直後から個別面談を繰り返し、キャリア形成にむけた意識を高めていきます。自治体等や農業関連企業との連携も深く、日常的に現場の情報を提供。さらに学内外のセミナーにより、情報だけでなく就農・就職のきっかけも得られます。ES作成・面接対策など就職活動サポートのほか大学編入希望者は個別に指導しています。
アグリビジネス科の奨学金
- 本校独自の奨学金制度もあります
- 「鯉淵学園奨学金(無利子)」は、月額2万円、3万円、5万円から選択できます。日本学生支援機構奨学金も利用可能。採用条件や申請方法等は、学生募集要項でご確認下さい。また、農林水産省 「農業人材力強化総合支援事業」の就農準備支援資金の交付対象です(詳細はお問い合わせ下さい)。
鯉淵学園農業栄養専門学校 アグリビジネス科のオープンキャンパスに行こう
アグリビジネス科のOCストーリーズ
アグリビジネス科のイベント
鯉淵学園農業栄養専門学校 アグリビジネス科の学べる学問
鯉淵学園農業栄養専門学校 アグリビジネス科の目指せる仕事
鯉淵学園農業栄養専門学校 アグリビジネス科の資格
アグリビジネス科の目標とする資格
- 毒物劇物取扱責任者<国> 、
- 危険物取扱者<国>
大型特殊自動車運転免許
小型車両系建設機械
小型フォークリフト作業免許
日本農業技術検定(3・2級)
農業簿記検定(3・2級)
鯉淵学園農業栄養専門学校 アグリビジネス科の就職率・卒業後の進路
アグリビジネス科の就職率/内定率 100 %
( 就職者数16名 )
アグリビジネス科の主な就職先/内定先
- 岩崎農園、アクト農場、筑波乳業、JA常陸、瑞穂農場、陸上自衛隊
※ 2024年3月卒業生実績
鯉淵学園農業栄養専門学校 アグリビジネス科の問い合わせ先・所在地・アクセス
〒319-0323 茨城県水戸市鯉淵町5965
TEL 029-259-2811(学務担当)
| 所在地 | アクセス | 地図 |
|---|---|---|
| 茨城県水戸市鯉淵町5965 |
「友部」駅からバス 茨城交通鯉渕学園下車 15分 |