酪農学園大学 農食環境学群
フィールドはキャンパス内から世界まで、4つの学類で学ぶ
| 学べる学問 |
|
|---|---|
| 目指せる仕事 |
|
| 初年度納入金: | 2026年度納入金(予定) 158万4000円~158万9000円 (循環農・食と健康・環境共生・農環境情報学類/入学金含む) |
|---|---|
| 年限: | 4年制 |
酪農学園大学 農食環境学群の募集学科・コース
人の生命を育む農畜産物の生産と、土地や水に代表される環境の関係を学び、永続的な「循環農学」を探究する
農環境情報学類
※2026年4月設置予定(構想中)
循環農法を基盤とし、DXやAIといった最先端の技術を活用して未来の地域と農業の創造に貢献できる人材を養成
地域データサイエンス領域
※2026年4月設置予定(構想中)
データを用いて持続可能な社会を実現するための、コンサルタントやブリッジャー(橋渡し役)となる人材を養成
アグリデザイン領域
※2026年4月設置予定(構想中)
地域産業のコーディネートや、地域の産業とその振興をマネジメントできる人材を養成
酪農学園大学 農食環境学群の学部の特長
農食環境学群の学ぶ内容
- 循環農学類
- ■生産から経営、経済まで「農」という産業のすべてを網羅
農家の方々とも密接に連携しながら農学全般を学びます。本学類の教員は、農業試験場をはじめとする学外のさまざまな人や機関とつながりがあり、新たな視点を得る機会を与えてくれます。
■「循環農法」環境に負担をかけない農業を探究する
人と自然が共生し、物質やエネルギーが循環するシステムをつくる「循環農法」を基本思想にして、これからの農業を学びます。
- 食と健康学類
- ■1年次には作物栽培や家畜に触れる農業実習で生産現場を体験
食品全般を理解するため、土から育てた作物が人の体の中で変化するまで、一連の流れを体験しながら学べます。1年次には畑に種をまいて育てた野菜の収穫を行い、また、牛や羊、鶏、豚などの家畜に触れて食品のもととなる生産現場を体験します。
■安心・安全な「食品」の製造・加工・流通から健康・医療分野までをカバー
食の分野は、安全性やアレルギーの問題、食品自給率の低下、高齢者向けの食品開発の必要性などさまざまな課題を持ち、食品にとどまらず健康・医療まで密接な関わりがあります。これらを体系的に学び、それぞれの専門性を深めていきます。
- 農環境情報学類〔2026年4月設置構想中〕
- 「農」×「テクノロジー」を基礎から学ぶ。農畜産物と加工品の44%を日本全国に輸送し、食料基地である北海道。酪農学園大学では、約90年前から資源を循環させて自然環境への負荷を考えた「循環農法」を取り入れ、北海道の酪農の発展に貢献してきました。また、現在では広大なキャンパスに加え、フィールドワークの舞台は海外まで広がり、豊富な実習・実験・演習によって知識と実学を両立しながら実践的な学びを展開しています。人のつながり、生命の循環、命の尊さを学ぶとともに、学生の自主性を促す教育プログラムを展開。共通教育(基盤教育・キャリア教育等)で培った力は、2年次以降の専門教育はもちろん、その先の人生にも必要となる「生きる力」につながります。
- 環境共生学類
- ■地球環境、生態系の仕組みやつながりを科学的に解明し、問題解決の方法を探る
環境とは人や生物を取り巻く総体で、守るのも壊すのも人の考え方次第です。野生の動植物に対して好き嫌いだけでなく、一つの生命として向き合い、すべての自然のつながりを理解する学びを行います。
■北海道から世界のフィールド実学まで教育を実践
4年間を通してたくさんのフィールドワークの機会があり、複雑な生態系を肌で感じながら学ぶことができます。学生の4人に1人が実習・調査・留学でアジアやオセアニア、欧米、アフリカなどの海外経験をしていることも本学類の特長です。
農食環境学群の資格
- カリキュラム自体が各種資格試験に対応!教員採用試験対策を展開する「教職課程」も設置
- 管理栄養士コースと獣医学類では、カリキュラムそのものが各種国家資格試験に対応しており、効率的に資格取得にチャレンジできます。また、教員免許については、農食環境学群の各学類に所属しながら教職課程に登録して取得する方法もあります。「教職課程」は、循環農学類と食と健康学類に設置されたもので、教員を目指す学生のために実践的なコミュニケーション能力を養う科目を展開し、教員採用試験に向けたプログラムを実施。卒業時に農業科の免許に加えて、中学校教諭免許状【理科】<国>・高等学校教諭免許状【理科】<国>または中
学校教諭免許状【社会】<国>・高等学校教諭免許状【公民】<国>の免許を取得することができます。
農食環境学群の施設・設備
- 学びのフィールドは広大なキャンパスと充実した設備
- 北海道の広大な大地と自然の恩恵をたっぷり受けた総面積135haもの広さを持つキャンパスは、190万都市・札幌から最寄りの大麻駅までJRで約15分。都市の利便性と豊かな自然環境を併せ持つ江別市にあります。南側には道立自然公園・野幌森林公園が広がり、大自然の宝庫でのフィールドワークをはじめ、道内各地の農家で農業実習を行うなど、北海道の環境を生かしたカリキュラムは本学ならではです。
酪農学園大学 農食環境学群のオープンキャンパスに行こう
農食環境学群のイベント

農・食・環境の分野から広がる、幅広い活躍のフィールドを学ぶ
農食環境学群のオープンキャンパス情報です。

農・食・環境の分野から広がる、幅広い活躍のフィールドを学ぶ
農食環境学群のオープンキャンパス情報です。
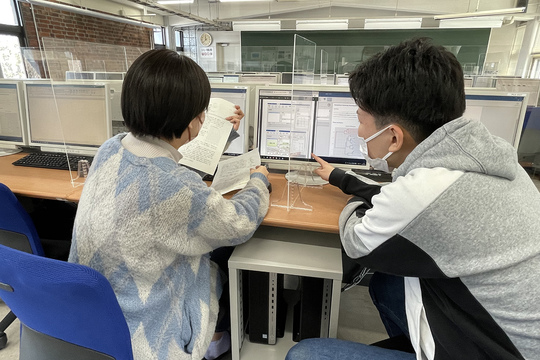
農・食・環境の分野から広がる、幅広い活躍のフィールドを学ぶ
文系・理系不問!農・食・環境に関する専門職をはじめ、なりたい自分を探そう。

農・食・環境の分野で活躍できるフィールドを知る!
文系・理系不問!農・食・環境に関する専門職を目指して、なりたい自分を探そう。
酪農学園大学 農食環境学群の目指せる仕事
酪農学園大学 農食環境学群の問い合わせ先・所在地
入試広報センター入試広報課
〒069-8501 北海道江別市文京台緑町582番地
TEL:0120-771-663 (フリーダイヤル)
| 所在地 | アクセス | 地図 |
|---|---|---|
| 北海道江別市文京台緑町582番地 |
「大麻」駅南口から徒歩 約10分 「新さっぽろ」駅からJR・夕鉄バス 約20分 とわの森三愛高校前下車徒歩 5分 「新さっぽろ」駅からJR・夕鉄バス 約20分 酪農学園前下車徒歩 5分 「新さっぽろ」駅から夕鉄バス 約20分 酪農学園構内下車徒歩 1分 |
