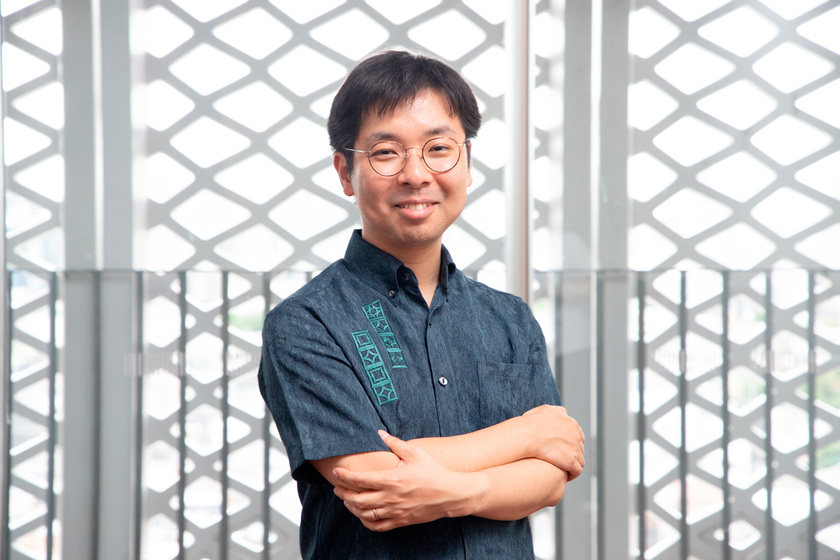
こんな先生・教授から学べます
現代社会とアートをつなぐ、橋渡し役として活躍する先生
舞台芸術のドラマトゥルギー(演劇論・戯曲論)を専門に、現代の日本とドイツ語圏で、舞台芸術作品がどのようなプロセスで創作されているのか、劇場を取り巻く環境などを比較研究しています。ドイツの劇場には「ドラマトゥルク」と呼ばれる専門職があり、上演作品の選定、観客とのコミュニケーション、作品の分析や演出への助言など、企画段階から作品制作まで一貫して関わります。美術館におけるキュレーターに似た役割と言えるかもしれません。研究活動と並行して、私自身もこれまでにドラマトゥルクの仕事のほか、劇場や国際舞台芸術祭などでプロデューサーやコーディネーターの仕事に携わってきました。現代社会と芸術文化の橋渡し役としての活動を続けながら、学生とともに社会におけるアートの役割を探究しています。

「舞台芸術産業論」の授業では、舞台を手掛けるプロダクションや劇団からゲストスピーカーを招いています
アート展をゼロから企画!学生が自ら考えてやり遂げる経験が成長につながります
「現代社会とアートをつなぐ」をテーマとする横堀ゼミ。音楽や演劇を中心としたアートの基礎知識を身につけて、アートの社会的な役割について考えます。フィールドワークや実習を積極的に取り入れているのも特徴で、劇場やアートイベントに足を運び、会場の運営方法や料金、来場者満足度などをリサーチし、批評的な視点から考察します。また、学びの一環としてイベントの企画・制作にも取り組んでいます。2024年度はゼミ生の一人が発案した、学生生活で体験したギリギリ耐えたエピソードを展示する『ギリギリたえたよ展』を実施しました。

オープンキャンパスの来場者に向けて開催した『ギリギリたえたよ展』は、高校生の共感を得て大好評!
アートやエンタメ、舞台制作の裏側に興味がある人におすすめ
研究テーマは、アイドル、K-POP、2.5次元俳優など何でもOK! 4年間の学びを通して、自分にとって「面白い」と思えることを見つけ、その「面白さ」を人に届けるスキルや発想力を身につけましょう。

ゼミでは学生の発案で、映画の応援上映や新宿のテント演劇の観劇など、多彩な活動をしていると話す横堀先生
横堀 応彦准教授
専門:演劇学、文化政策学
東京藝術大学大学院音楽研究科博士後期課程修了。博士(学術)。ライプツィヒ音楽演劇大学大学院ドラマトゥルギー科にて研究滞在(ロータリー財団補助金奨学生)。東京芸術劇場での勤務を経て現職。担当する科目は、2~4年生のゼミのほか「演劇論」「舞台芸術産業論」「アーツマネジメント」など。
※この画面の情報は、すべて取材した時点でのものになります。
この学校のおすすめ記事
-
 在校生映画を通して、人に感動や気づきを届けられる仕事に携わりたい!文学部 現代文化表現学科
在校生映画を通して、人に感動や気づきを届けられる仕事に携わりたい!文学部 現代文化表現学科 -
 卒業後システムの困り事に駆けつける!ホームドクターの様な存在を目指していますマネジメント学部 営業
卒業後システムの困り事に駆けつける!ホームドクターの様な存在を目指していますマネジメント学部 営業 -
 在校生ニュースや街ナカのお店を分析して、モノを売る仕組みを学んでいますマネジメント学部 マネジメント学科
在校生ニュースや街ナカのお店を分析して、モノを売る仕組みを学んでいますマネジメント学部 マネジメント学科 -
 在校生商品を売る仕組みを考える「マーケティング」は発見が多くて面白い!マネジメント学部 マネジメント学科
在校生商品を売る仕組みを考える「マーケティング」は発見が多くて面白い!マネジメント学部 マネジメント学科
