
こんな先生・教授から学べます
医療・福祉分野に貢献するロボットを創造する先生
「私たちの研究室では、ロボット・メカトロニクス・AIなどの技術を駆使して高齢者や障害のある方々の日常生活の質を向上させる装置やシステムの研究・開発を行っています。その一例が「高齢者用パーソナル・モビリティーの開発」です。高齢者が外出時に4輪の歩行器を押している姿を目にしたことがある人は多いと思いますが、運動能力が低下している高齢者にとっては小さな石や段差も転倒リスクにつながる障害物。そこで小型カメラを搭載し、危険個所をプロジェクションマッピングで知らせる歩行器の実用化を目指しています。また、固まってしまった関節の動きをサポートする「上肢補助装具」や「短下肢装具設計支援システム」「失語症患者のためのリハビリ対話システム」など、医療・福祉分野を最新技術で支えるためのさまざまな挑戦を続けています。」

プロジェクションマッピングを用いて周囲の障害物を知らせることで転倒を防止する歩行補助器を開発中
多様な技術分野を複合的・融合的に学ぶ実験科目
医療・福祉機器の開発には、機械、電気・電子、情報処理など多分野の知識や技術を融合させる必要があり、「生命医工学実験I」の授業では、光を使って血流量や心拍数などを計測する光電脈波計(簡易版)の実作を通して、各分野の技術を体感するとともにメカトロニクス・システムとして構築する手法を学んでいく。「実験科目はアイデアを出し合うグループワークも多いため、コミュニケーション能力を高める場にもなっています」と語る高木先生の信条は“迷った時は手を動かす”。それが浸透しているせいか教室は常にアクティブな雰囲気だ。

写真はインドネシアで行われている講義で、組み込みプログラミングを用いたグループワークの様子
AIやロボットを活用した装置の開発技術が基礎から学べます!
「医療や福祉は人の生命や生活に直接関わる大変やりがいのある分野です。「人の役に立ちたい」「困っている人を助けたい」という方は、是非、この分野に進んでください。一緒に学べる日を楽しみにしています!」

「カイツブリという鳥の動きを取り入れた“生体模倣型水中・水上ロボット”の開発にも着手しました」
高木 基樹准教授
専門分野:生体医工学、医療福祉工学、知能ロボティクス
芝浦工業大学 システム理工学部 機械制御システム学科卒業。2010年~2012年、名古屋工業大学 特任研究員。2012年~2016年、岩手大学 三陸復興推進機構 特任研究員。2016年~2017年、岩手大学 理工学部 特任研究員。2017年~2019年、帝京大学 理工学部 講師。2019年より現職。
※この画面の情報は、すべて取材した時点でのものになります。
この学校のおすすめ記事
-
 在校生医師と患者にとってより良い医療機器を作れるように頑張ってます!システム理工学部 生命科学科(2026年4月、生命科学課程へ改組予定)
在校生医師と患者にとってより良い医療機器を作れるように頑張ってます!システム理工学部 生命科学科(2026年4月、生命科学課程へ改組予定) -
 卒業後技術と仕事を通して、人と社会に貢献しているという実感がいまのやりがいですシステム理工学部 生命科学科(2026年4月、生命科学課程へ改組予定) 技術者
卒業後技術と仕事を通して、人と社会に貢献しているという実感がいまのやりがいですシステム理工学部 生命科学科(2026年4月、生命科学課程へ改組予定) 技術者 -
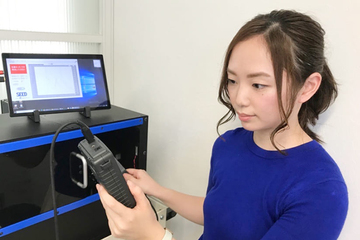 卒業後海外の研究者と組んで、先進分野の商品開発に力を注いでいます!システム理工学部 生命科学科(2026年4月、生命科学課程へ改組予定) 医療機器開発技術者
卒業後海外の研究者と組んで、先進分野の商品開発に力を注いでいます!システム理工学部 生命科学科(2026年4月、生命科学課程へ改組予定) 医療機器開発技術者 -
 先生・教授環境中の有害物質の発生源を分析化学で解明する先生システム理工学部生命科学課程 川島 洋人教授
先生・教授環境中の有害物質の発生源を分析化学で解明する先生システム理工学部生命科学課程 川島 洋人教授
