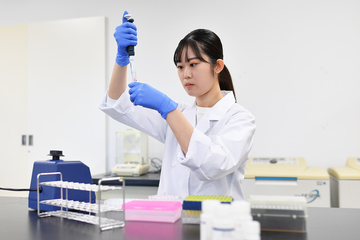こんな先生・教授から学べます
がん患者の「痛い」のサインを見逃さない先生
がん看護の中でも「認知機能の低下した高齢がん患者への疼痛緩和のための看護」を専門にしています。疼痛とは、医学用語で痛みのこと。痛みがあっても看護師にうまく伝えられない、患者さん自身が痛みを認識できない、看護師側に先入観があり患者さんの痛みに気づけないなど、認知機能の低下は疼痛ケアに大きな影響を及ぼします。多くの事例を分析し、現場の看護師からも聞き取りを行う中で、患者さんと看護師との関係性が痛みのアウトプットに影響することや、看護師同士や職種間のコミュニケーション不足でケアが上手くいかない場合があることに気づきました。そこで、看護師が交替勤務をする中でも患者さんの生活スタイルを共有し痛みやサインの発見につなげられるように、チェックシートをはじめとする教育プログラムを作成し、普及に努めています。

最新鋭の機器、患者役の人形…様々な設備が整った埼玉医科大学の環境は、櫻庭先生の研究にも活かされている
「分かる」「実感できる」その体験を積み重ね、「自分の言葉」で相手に語りかけられる看護師を目指す
櫻庭先生が担当するのは3年次の必修科目「成人看護学方法論III」と4年次の選択科目「パリアティブケア論」。どちらも、先生の現場での経験談を交えながら、分かりやすい授業を心がけているという。また、実習先の埼玉医科大学国際医療センターに隣接する環境を活かし、センターで働く認定看護師や専門看護師を招いて講義を行うことも多い。「看護師になった際に求められるのは、患者さんやそのご家族に自分の言葉で話しかけ、信頼関係を構築することです。そのためにも教科書的な知識だけでなく、学生の「実感」を大事にしています」

「もしも」にどう対応するか。カードゲーム形式で自他の価値観の違いを実感し、看護師としての幅を広げる
看護師という仕事の持つ可能性や素晴らしさを、皆さんと一緒に考えたい
看護師は患者さんの生活の維持向上に関わる職業です。それは医療職の中でも特に人生観が問われるとともに、看護師自身の人生を豊かにする可能性があるということ。「人生の豊かさとは何か?」を一緒に考えましょう!

「学生のうちに経験できることが人生の厚みを増してくれる。そこに大学で看護を学ぶ意味があると思います」
櫻庭 奈美 准教授
略歴/北海道、大阪府の大学病院で臨床経験を積む。その後、緩和ケア認定看護師、がん看護専門看護師を取得。認定看護師として病院で働いていた際、認知機能の低下によるがん患者の困難に直面したことから研究の道へ。大学院修了後教員経験を積み、2021年より埼玉医科大学にて成人看護学領域の指導に携わっている。博士(看護学)。
※この画面の情報は、すべて取材した時点でのものになります。