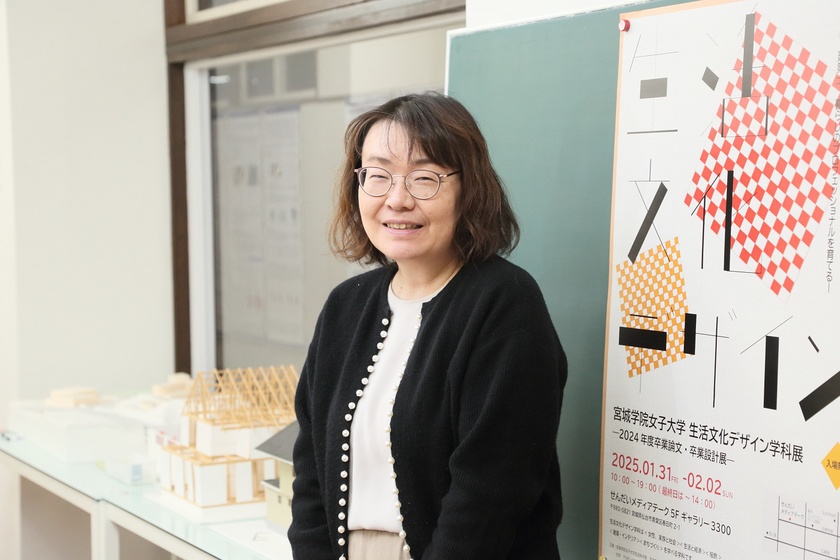
こんな先生・教授から学べます
誰もが仕事と生活を楽しめる社会へ視野を広げてくれる先生
経済成長の鈍化で日本は共働きしなければ十分な生活水準が保てなくなっており、共働きが当たり前になる一方、家事や子育ての分担が進んでいません。又親たちは子どもが小さいうちから習い事を複数させたり、中学受験など教育投資もさかんです。私は現代の親たちが家事や子育てをどう分担しているのか研究しています。こういった研究は、大学院生の時に出産し子育てしたり、親の闘病を支えた私の経験から来ています。最近は男性の家事実践についても研究しています。今の家族のリアルな姿を伝えることが、これから就職する学生たちのライフコース選択のエッセンスになればと思います。離婚率や年金を見ても、総合的に日本はまだ女性に厳しいところも。ワークとライフがバランスした社会に向けて個人でできることと課題を一緒に考えていきたいですね。

社会調査の授業ではパソコンソフトで大規模なデータ分析も。学生自らが内容を考察し実施する授業も好評
家族や学校で感じた身近な疑問がスタート。社会の当たり前を問い直す気づきの連続
授業では家族論やジェンダー論、ライフコース論、社会調査法演習などを担当する藤田准教授。海外の制度との比較や量的・質的な調査法などを指導しています。ゼミでは、3年後半から学生それぞれの興味に従って研究を行い、発表・ディスカッションを実施。「学生自身が興味を持ったテーマであれば、研究が楽しくなり、オリジナルな発想が生まれる」という考えのもと、研究テーマは学生の自主性を尊重。「社会学では自分の手と足を動かして、生のデータを取ってくることが大事」をモットーに、アポを取るところから指導してくれます。

人々の生き方について深く聞き取るインタビュー調査。見えなかった意識が見えてくる社会学の魅力のひとつだ
女性は損してる?私たちが十分に能力を発揮できる社会を考えてみませんか
ジェンダー論や家族社会学を学ぶことは、自分自身や育った環境を俯瞰で見ることができ、生きる力に繋がります。家族や学校で感じるモヤモヤの原因は何か。それは変えられないものなのか。一緒に考えてみませんか。

読書や食べ歩きが趣味。仙台に引っ越してきてから始めたガーデニングでは、季節の花々を楽しんでいる
藤田 嘉代子 准教授
家族社会学、ジェンダー論専門。大阪教育大学教育学部卒業。大阪大学大学院人間科学研究科後期博士課程修了。2015年大阪大学男女協働推進センター助教を経て2017年より現職。大阪府生まれ。
※この画面の情報は、すべて取材した時点でのものになります。
この学校のおすすめ記事
-
 先生・教授未来の扉を開く鍵。ICTの活用を教えてくれる先生現代ビジネス学部現代ビジネス学科 舛井 道晴 准教授
先生・教授未来の扉を開く鍵。ICTの活用を教えてくれる先生現代ビジネス学部現代ビジネス学科 舛井 道晴 准教授 -
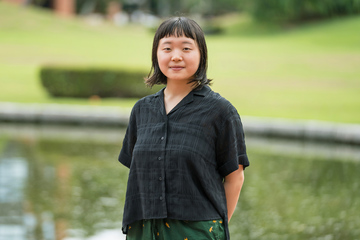 在校生海外の方と積極的なコミュニケーションが取れるように英語の勉強中!学芸学部 人間文化学科
在校生海外の方と積極的なコミュニケーションが取れるように英語の勉強中!学芸学部 人間文化学科 -
 先生・教授発達障害への多様な支援を通して共生社会を目指す先生教育学部教育学科児童教育専攻 梅田 真理教授
先生・教授発達障害への多様な支援を通して共生社会を目指す先生教育学部教育学科児童教育専攻 梅田 真理教授 -
 先生・教授教師に大切な「共生」の教育観を教えてくれる先生教育学部教育学科健康教育専攻 戸野塚 厚子教授
先生・教授教師に大切な「共生」の教育観を教えてくれる先生教育学部教育学科健康教育専攻 戸野塚 厚子教授
