全国のオススメの学校
-
大阪人間科学大学保健医療学部2024年4月、「社会創造学科」誕生!私立大学/大阪
-
鹿児島医療技術専門学校言語聴覚療法学科育成したいのは時代の要請に応える医療・福祉のプロフェッショナル専修学校/鹿児島
-
大和大学白鳳短期大学部リハビリテーション学専攻教育・保育・看護・リハビリのスペシャリストになる!国家資格取得で抜群の就職実績私立短期大学/奈良
-
神戸医療福祉専門学校三田校言語聴覚士科業界との連携で就職率100%!関西唯一、リハビリ・救急救命・義肢装具分野が揃う学校専修学校/兵庫
-
山口コ・メディカル学院言語聴覚学科理学療法・作業療法・言語聴覚療法。豊かな人間性を身につけたリハビリの専門家を育成専修学校/山口
言語聴覚士は生身の人間を相手に仕事をするので、人間そのものに興味や関心をもてる人、コミュニケーションが好きな人が向いています。
また、リハビリはすぐに結果が出るものではなく、言語聴覚士と患者さんの双方が地道に努力を重ねることで少しずつ変化が出てくるものなので、何ごとにも根気よく取り組めるかどうかも重要です。
リハビリは辛く苦しいものであることも多いので、患者さんの中には「こんなことしたくない!」とネガティブになり、周囲に対して心を閉ざしてしまう人も。そんな患者さんの心に寄り添い、相手の気持ちに立った行動・発言ができる思いやりも、言語聴覚士として働くうえでは大切になります。
人とコミュニケーションすることが好き
リハビリとは目の前の患者さんに向き合う作業です。リハビリの進み具合は、プログラムの良し悪しだけでなく、コミュニケーションのしかたによっても大きく変わってきます。
同じプログラムを組んだとしても、患者さんが違えば、結果も違ってくるでしょう。そのため、病状だけでなく患者さんの性格や趣味・嗜好、そして「今、この人は何を考えているんだろう?」という点を知りにいくことが、患者さん一人ひとりに寄り添う上で大切なことになります。
人との何気ない会話を楽しめる人、他人に興味をもてる人には適性があると言えるでしょう。
根気強さ
相手のペースに合わせて根気よくリハビリを行っていく忍耐強さも必要です。なかなか結果に結び付かないと焦ることもあるかもしれませんが、じっくり腰を据えて患者さんと向き合うことで、少しずつ改善に向かうものだと心得ておきましょう。
共感する力
患者さんには、自分が伝えたいことをうまく伝えられないことで、ストレスを溜め込んでしまっている人が多くいます。また、病気や事故で障がいをもつことになった患者さんには、「昨日まで当たり前にできていたことが、できなくなってしまった」と絶望感の中にいる人もいます。
そんな人たちの心の声に耳を傾け、受け止めてあげられるやさしさも必要になってくるでしょう。
観察眼
リハビリでは、患者さんの発音やちょっとした口の動きなどから状態を見極め、改善方法を探っていきます。そのため、観察力や注意深さも重要なスキルになります。また、言葉で自分の想いをうまく伝えられない人が多いので、表情やしぐさなどから、意思を読み取る繊細さも必要です。
相手が求めていることを見極める力
患者さんが自分らしい生活を取り戻すために、リハビリによってどんなことができるようになったらいいのかを考えることも言語聴覚士の役割。そのためには、患者さんやご家族とのコミュニケーションを通して、「今、患者さんが困っていることは何か?」「退院後、どんな生活を送りたいのか?」を正しく見極める力も大切になります。
協調性
高い専門性をもつ言語聴覚士ですが、単独でリハビリを行うことは少なく、他職種のスタッフと連携していくシーンが多く発生します。例えば医師、看護師、理学療法士や作業療法士、介護スタッフ、管理栄養士など…。患者さんに関する情報を共有し合ったうえで、それぞれが自身の専門分野の知識と技術を発揮し、協力して治療を進めていくこと。それが、適切かつスムーズな治療につながっていくのです。
向上心
言語聴覚療法とかかわりの深い脳科学、生命科学、認知科学などの分野では、日々新しい研究成果が発表されています。そのため、言語聴覚士は資格取得後もこれらの最新情報をキャッチアップし、臨床へ柔軟に取り入れていくことが求められます。
主には勉強会などに参加し、新しい情報を得ることになりますので、そういった場に足を運ぶ積極性も大切になります。
言語聴覚士になるには?
言語聴覚士の仕事について調べよう!
言語聴覚士の先輩・内定者に聞いてみよう

言語聴覚士科

言語聴覚学科 卒

言語聴覚療法学科
言語聴覚士を育てる先生に聞いてみよう

言語聴覚士科 昼間3年制

リハビリテーション科学部言語聴覚療法学科

言語聴覚士科
言語聴覚士を目指す学生に聞いてみよう

リハビリテーション学部 リハビリテーション学科 言語聴覚学専攻
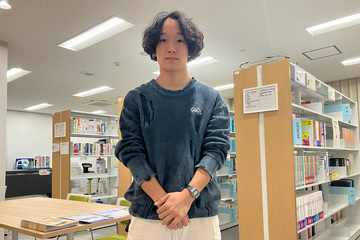
リハビリテーション学部 言語聴覚療法学科

言語聴覚療法学科



