全国のオススメの学校
-
聖隷クリストファー大学リハビリテーション学部周辺環境に恵まれたキャンパスで学べる、保健医療福祉・教育の総合大学私立大学/静岡
-
西武学園医学技術専門学校 東京池袋校言語聴覚学科都心の池袋でスピーチセラピストになる!聞こえ・のみこみ・ことばのスペシャリスト専修学校/東京
-
昭和医科大学言語聴覚療法学専攻2025年4月1日、昭和大学は「昭和医科大学」に校名を変更しました。私立大学/東京・神奈川・山梨
-
愛知学院大学健康科学科中部圏でも有数の規模と伝統を誇る総合大学私立大学/愛知
-
北海道医療大学言語聴覚療法学科医療系総合大学でチーム医療を学ぶ。2028年にFビレッジ内の新キャンパスに移転。私立大学/北海道
「言語聴覚士国家試験」の受験資格を得るためには、文部科学大臣が指定する学校(3~4年制の大学・短大)または都道府県知事が指定する言語聴覚士養成所(3~4年制の専修学校)を卒業する必要があります。
言語聴覚士は仕事の領域が広いため、幅広い専門知識と豊富な実習経験を積んでおきたいなら4年制の学校、できるだけ早く資格を取得して現場に出ることを目指すなら3年制の学校が候補になるでしょう。
また、養成課程のない大学を卒業したあと、指定された大学・大学院の専攻科または専修学校(2年制)を卒業することで、受験資格を得るルートもあります。
養成施設で学ぶこと
コミュニケーション障がいの病態や医学的処置といった医学的知識はもちろんのこと、人間の心の働きを理解するための心理学や認知科学、ことばや音声のしくみについての言語学や音声学、社会福祉や教育についての科目がカリキュラムとして用意されています。
1年次は講義の割合が多くなりますが、徐々に演習や実習が増え、病院などでの臨床実習も行われます。ほかの医療・リハビリ系の職種と同じく、実習に重きを置いているのが、言語聴覚士養成施設の特徴です。
国家試験に向けての準備は、最終学年の秋ごろにスタートすることが多いようです。
4年制大学
総合大学・医療福祉大学・保健科学大学などの医療保健学部や人間科学部に、「言語聴覚学科」や「言語聴覚学専攻」が設置されています。そのため、言語聴覚療法と密接な関係をもつ医学や心理学などを専門にする学部・学科と連携が深い場合も多く、言語聴覚療法を多面的に深く学ぶことができます。
また、言語聴覚士になるために必要な専門知識に加え、広く一般教養を身につけることができるのも4年制大学ならでは。言語聴覚士がリハビリを行う患者さんは、子どもからお年寄りまであらゆる世代にわたります。患者さんとの信頼関係を結ぶには、まずはコミュニケーションが大切。共通の話題で盛り上がれる引き出しの多さも、プロとしての武器になるのです。
4年間の大学生活で存分に学び、遊び、人と交流し、さまざま人生経験を積んでおくことも、1人の人間としての深みを出すために有効な手段となるでしょう。
3年制短大
4年制大学と同じく、言語聴覚療法の専門知識にとどまらず、一般教養まで幅広く学べることが短大の特徴。ただし、大学よりは1年間学ぶ期間が短くなりますので、「基礎知識&技術を身につけたら、なるべく早く現場に出たい」という人におすすめの進路先です。
さまざまな学科がある学校なら、自分とは違った分野を勉強している人、興味や趣味をもった人にも出会いやすいはず。周囲から受けた刺激や人との交流で培ったコミュニケーション力も、言語聴覚士として働く際に役に立つでしょう。
専門学校(4年制・3年制)
言語聴覚士の国家資格を取得し、現場に出ることを最大の目的とした、実践的なカリキュラムが組まれていることが専門学校の特徴です。大学や短大以上に、病院などでの「臨床実習」や「国家試験対策」に力を入れている学校も多いので、「絶対に言語聴覚士になりたい!」「実践的な学びの中から、現場ですぐに役立つ力を身につけたい!」と考えている人に特にフィットするでしょう。
言語聴覚士を目指す社会人が専門学校に通うケースも多く、さまざまな年代&バックグラウンドをもった人と交流できることも魅力です。
専門学校といっても学校ごとに個性がありますので、まずはオープンキャンパスや体験入学に積極的に参加し、学校の特徴や雰囲気、資格取得&就職へのバックアップ体制をチェック&比較検討することをおすすめします。
言語聴覚士になるには?
言語聴覚士の仕事について調べよう!
言語聴覚士の先輩・内定者に聞いてみよう

言語聴覚士科

言語聴覚学科 卒

言語聴覚療法学科
言語聴覚士を育てる先生に聞いてみよう

言語聴覚士科 昼間3年制

リハビリテーション科学部言語聴覚療法学科

言語聴覚士科
言語聴覚士を目指す学生に聞いてみよう

リハビリテーション学部 リハビリテーション学科 言語聴覚学専攻
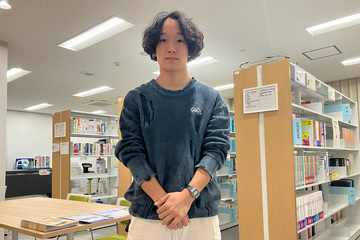
リハビリテーション学部 言語聴覚療法学科

言語聴覚療法学科



