全国のオススメの学校
-
専門学校 徳島穴吹カレッジ保育・幼児教育学科16学科から探す未来。シゴトに「最適」な実力を、「最短」で身につける専修学校/徳島
-
智泉幼児保育専門学校保育学科専門知識や技術を身に付け、即戦力として活躍できる「保育士」「幼稚園教諭」へ!専修学校/大分
-
椙山女学園大学保育・初等教育専修「私を選ぶのは、わたし。」2024年、3学部5学科が誕生し、7学部11学科を展開。私立大学/愛知
-
山口短期大学児童教育学科山口と福岡、2つのキャンパス!保育、幼児・初等教育、ITの専門家を養成私立短期大学/山口・福岡
-
北陸福祉保育専門学院こども学科(2年制)附属園があるから子どもが身近。未来を育てる保育士、幼稚園・小学校・養護教諭に専修学校/新潟
近年は保育の現場や給与・待遇に関する負の側面がクローズアップされてきましたが、少しずつ改善が進んでいます。保育士それぞれが自身の知識やスキルをよりブラッシュアップし、世の中が保育士の仕事の専門性を再認識することで、保育士の社会的立場はきっと今まで以上に高まっていくはずです。
働き方が変わり保育所へのニーズも変化
ある認可保育所の所長は、「保育所への要求がどんどん多様化している」と語ります。
例えば、「もっと早い時間から子どもを預かってほしい」「もっと遅くまで子どもを預かってほしい」というのはよく聞かれる声です。
ある保育所では7:30~19:00という長時間で保育を実施していますが、フルタイムで働く保護者が増え、始業時間に間に合わない&お迎えが間に合わなケースが増えているのが一因になっているそうです。また、ショッピングセンターや携帯ショップなどのサービス業従事者が増えていることから「土日も子どもを預かってほしい」という要望も多くなっています。
さらに、「リフレッシュ保育」と呼ばれる一時保育へのニーズが大きくなっているのも一つの特徴だと言います。リフレッシュ保育とは、保育所に子どもを預けていない(預けられない)家庭の子どもを一時的に預かる公的な事業のことです。指定の公立保育所が月に2回ほど実施するもので利用には事前予約が必要になるのですが、毎回希望者が殺到し、「予約開始と同時にすぐに定員がいっぱいになってしまって全然利用できない」という状況が生まれています。
リフレッシュ保育は育児疲れの解消を図るためにスタートした支援サービスですが、そのニーズに体制が追いついていない現状があるようです。
保育サービスの拡充には待遇改善が必要
では、それらのニーズをすべて受け止めていくことは可能かというと、難しいのが現状です。なぜなら、より多くの子どもをより柔軟に預かるためには、保育士の数が足りないからです。認可保育所や認証保育所では、一人の保育士が面倒を見ることのできる子どもの人数が定められています。その基準を満たすギリギリの人員でシフトを回している施設では、預かる子どもや時間を増やすために保育士を新たに採用しなくてはなりません。ところが、人員を増やそうにも、保育士志望者の減少と保育士の離職が大きな壁となり、難しいのが現状です。
保育士の待遇改善に向けての政府の取り組み
現場の声を受け、政府は2013年に給与・待遇改善に向けての取り組みを開始しました。なかでも注目すべきなのは、「処遇改善手当」の増額です。
処遇改善手当とは、保育士の給与を底上げすることを目的に、政府が各保育所に配布している補助金のことです。2013年以降、保育士1人あたり月額14%(約4万4000円)の給与改善を実施。2022年2月からはさらに3%(約9000円)の給与引き上げ措置もとられています。
また、中堅保育士の離職に歯止めをかけるべく、保育士経験がおおむね7年以上&指定の研修を受講した保育士を対象にした「副主任保育士」「専門リーダー」の職を新設。それぞれに月額最大4万円を支給することを定めています。また「職務分野別リーダー」には、月額最大5000円が加算されます。
ほかにも、政府とは別に給与に上乗せするための補助金を支給したり、借り上げ宿舎の家賃を全額補助したりと、独自の処遇改善をはじめている自治体もあります。
保育士に求められるスキルにも変化が
保育士の給与・待遇改善に向けての具体的な取り組みは、今後もしばらく続くと予想されます。これらの取り組みが世の中に広く知られるようになれば、保育士になりたいと考える人は増えてくるかもしれません。
そうした状況で、これから保育士を目指すうえで意識しておきたいのが、保育士に求められるスキル・レベルも以前とは変わってきているという点です。例えば、「副主任保育士」に認定されるには、「職務分野別リーダー」を経験したうえで、「マネジメント」について研修を積むほか、「乳児保育」「幼児教育」「障がい児保育」「食育・アレルギー」「保健衛生・安全対策」「保護者支援・子育て支援」の研修を修了する必要があります。看護師の世界でも、がんケアを専門にする「専門看護師」がいるように、保育の世界でも各分野のスペシャリストを養成する動きが進んでいるのです。
また、保育士の採用面接では、「子どもが好き」「保育に情熱がある」というのは当然として、「情緒の豊かさ」「誠実さ」「コミュニケーション力」を重視するという現場の声も聞かれます。
最近は、育児疲れやストレスによる精神状態の不安定さから、「子どもの面倒を十分に見てあげられない」「育児がつらい」「子どもとうまく関係が築けない」という保護者が増えており、彼らのケアを行っていくことも保育士が担うべき大きな役割になっていす。なぜなら、保護者を守ることは、その子どもを守り育むことにもつながるからです。
保育士になるには?
保育士の仕事について調べよう!
保育士の仕事についてもっと詳しく調べてみよう!
保育士の先輩・内定者に聞いてみよう

社会福祉学部 保育児童学科(2018年4月より保育児童学部 保育児童学科へ)

保育学科 こども保育コース卒
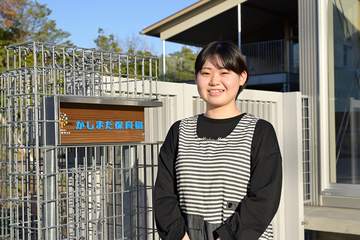
保育士コース(2年制) 卒
保育士を育てる先生に聞いてみよう

こども未来学科

こども学科

こども学科
保育士を目指す学生に聞いてみよう

保育科

保育分野 こども保育士コース

保育士・幼稚園教諭コース
関連する仕事・資格・学問もチェックしよう
関連する記事
-
 福祉・介護に関わる仕事10選!仕事内容、資格、やりがいを職種別に紹介
福祉・介護に関わる仕事10選!仕事内容、資格、やりがいを職種別に紹介「超高齢化社会」に突入した日本では、今後ますます高齢者が増加。 介護を必要とする人たちも増えていくなかで、福祉・介護職が果たす役割と人材の確保は、今まで以上に重要になると考えられている。 「人の役に立ちたい」という気持ちと同時に、高い専門性や資格が求められる仕事が多いこの分野。 どんな仕事・職場があ …
-
 幼稚園教諭ってどんな仕事? 保育士との違い・やりがいを徹底比較!
幼稚園教諭ってどんな仕事? 保育士との違い・やりがいを徹底比較!子どもが好きで、将来は幼稚園の先生になりたいと思っているキミ! 「幼稚園の先生にあこがれているけど、保育士の仕事もいいかな…」なんて、迷ったりしていない? そもそも幼稚園教諭と保育士ってどう違うのか、知ってる? そこで幼稚園教諭と保育士の資格のことや仕事内容、やりがいを解説! …
-
 子どもに関わる仕事8選!保育士、幼稚園教諭、心理士etc.必要な資格と仕事内容を解説
子どもに関わる仕事8選!保育士、幼稚園教諭、心理士etc.必要な資格と仕事内容を解説保育士、幼稚園教諭をはじめとする子どもに関わる仕事は、「子どもが好き!」という高校生にとっては魅力的な進路の一つ。 その一方で、乳幼児期の心と体の成長を支援するための高い専門性も必要とされるので、プロフェッショナルとしてのやりがいも十分。 子どもの保育や教育への関心が高まるなか、注目の職種、活躍の場 …
-
 【WEBオープンキャンパスレポ】忙しくても大丈夫。1時間で学校の様子&授業内容がわかった!
【WEBオープンキャンパスレポ】忙しくても大丈夫。1時間で学校の様子&授業内容がわかった!気になる学校があるけど、忙しくてなかなかオープンキャンパスに行く時間が取れないという人も多いのでは? 今回は、そんな悩みをもつ高校生が、オンラインで参加できる「WEBオープンキャンパス」を体験。 自宅にいながら効率的に情報収集できちゃう「WEBオープンキャンパス」。その様子をレポートします! <At …
-
 専門職として期待が高まる保育士!ニーズに応える人材になるには?
専門職として期待が高まる保育士!ニーズに応える人材になるには?「子どもが好き!」という高校生に人気の保育士 高校生の「なりたい職業ランキング」では、いつも女子部門の上位に来る人気の職業の保育士。 待機児童問題や保育士の人手不足が話題になることも多いように、ニーズは高まる一方だ。 「子どもが好き!」という高校生にとっては、魅力のある将来の選択肢の一つ …


