全国のオススメの学校
-
日本女子体育大学体育学部スポーツ・ダンス・健康・幼児教育。自分が好きな分野をじっくり学び、将来を築きます私立大学/東京
-
山口大学教育学部国立大学/山口
-
IPU・環太平洋大学(通信教育課程)教育経営学科実学教育にこだわった通信教育で、教員免許取得を目指す私立大学/岡山・北海道・宮城・千葉・愛知・大阪・兵庫・広島・福岡
-
桐蔭横浜大学スポーツ教育学科夢中になれる学びがここにある。情熱的な学生生活を過ごそう。私立大学/神奈川
-
国学院大学北海道短期大学部幼児・児童教育学科国学院大学の北海道キャンパス2年間+編入学で渋谷キャンパスの道も!私立短期大学/北海道
どんな職業にも共通しますが、社会人になってからも日々の情報収集をはじめ、さまざまなことに興味をもつことが大切です。ここでは、教諭が広いアンテナを張っていろいろなことに好奇心をもちながら、児童の目線に立つことの大切さを考えていきましょう。
社会の出来事に興味をもち、情報を備蓄する
世の中で今どんなことが問題になっているのか、その問題はどうして起きたのか、問題を解決できない理由は何なのか、といったように、教諭は常に幅広い分野にアンテナを張って新しい情報を仕入れていかなければなりません。
6歳~12歳の児童はまだ幼い子どもですが、その感性は驚くほど柔軟。世の中で起こっているできごとやはやりをすばやく察知し、トレンドに精通する“ウォッチ力”をもっています。そのため教諭も感度の高いアンテナを張る必要がありますが、それは単に情報を仕入れれば良いということではなく、数年前、現在、未来といった時間軸の中、問題がどのように変化しているかという目線や思考回路で、世の中の今をとらえていくことが大切です。
こうした情報収集によって教諭は子ども以上に進化、深化していかなければならないため、広い視野や科学的な思考回路を普段から養っておきたいもの。そうした力が養われると、「去年と同じ方法やプリントではなく、今年はこうアップデートしていこう」と具体的なアイデアが浮かんでくるようになります。
ここで、ある小学校教諭が肝に銘じている言葉「備蓄は必ず枯渇する」をご紹介しましょう。その先生はこう言います。
「〈備蓄は必ず枯渇する〉は、防災の教訓で使用されることが多いのですが、蓄えたものも月日が経てば使用期限切れになってしまいます。常に新しいことを補充、仕入れ続けなければならないという、教師の日々の活動や姿勢にも当てはまる言葉なのです」
広い視野や科学的な思考回路を養うため、その教諭は常に〈備蓄は必ず枯渇する〉の言葉を戒めにして教壇に立っていると言います。
社会の出来事に興味をもち、情報を備蓄する
私たちは、気づかぬうちに子どもから大人へと成長します。その成長過程で、子ども目線で見ていたものを、いつしか大人目線で見るように変化していきます。児童の目線と大人の目線では見える世界が異なるため、小学校教諭は常に児童の目線に立つことが求められますが、子ども目線を保つにはどのような方法があるのでしょうか。
例えば、アニメの人気キャラクター、はやりのゲーム、地方伝承、昔話、妖怪などの知識を蓄えることも、子ども目線を保つための秘訣です。驚くほど柔軟な感性と高い吸収力をもつ児童は、メディアやいろいろな本から幅広い情報を瞬時にキャッチする特技をもっています。ある曲がヒットすると、その曲のフレーズや振り付けをあっという間に覚えてしまうことも、大人にはまねできない子どもならではのスゴさです。そうした意味でも、最新のヒット曲を音楽の授業に使用すると児童は強い反応を示すので、ヒットチャートやアニメソングの知識の蓄えは、教諭にとって大きな武器になります。
さらに、児童が何気なく交わしている会話の中で人気アニメのキャラクター名が出てきたとき、教諭が「なにそれ?先生は知らない」といった反応を示してしまうと、児童に「先生はそんなことも知らないの」と思われかねません。逆に、マニアックな妖怪について教諭が知っていたら、きっと児童は羨望のまなざしを向けてくることでしょう。このように、教科とは関連しない知識が思わぬところで児童との絆を深めるきっかけにもなるので、さまざまな分野や領域に興味をもち、普段から児童の目線を養っておくようにしましょう。
小学校教諭になるには?
小学校教諭の仕事について調べよう!
小学校教諭の仕事についてもっと詳しく調べてみよう!
小学校教諭の先輩・内定者に聞いてみよう

国際こども教育学部 国際こども教育学科(2025年4月からこども教育学部 こども教育学科)

人間生活学部 児童教育学科(現:教育人文学部 児童教育学科)
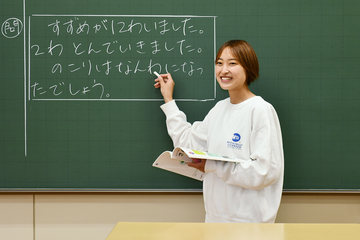
明星大学通信教育課程 小学校教員コース
小学校教諭を育てる先生に聞いてみよう

人間科学部 人間科学科 初等教育保育専攻・初等教育コース

教育学部教育学科

文学部児童教育学科
小学校教諭を目指す学生に聞いてみよう

人文学部 子ども教育学科

文学部 児童教育学科

人間学部 子ども発達学科
関連する記事
-
 教育関係の仕事とは?社会の未来を担う人を育てる【教育に関わる仕事21選】
教育関係の仕事とは?社会の未来を担う人を育てる【教育に関わる仕事21選】教育関係の仕事といえば、真っ先に思い浮かぶのは学校の先生だろう。   しかし、先生以外にも、地域、教育系NPO、民間企業、塾・予備校などに属する多くの専門家が、時に学校と協力しながら児童や生徒の教育に携わっている。   その仕事の広がり、個々の仕事の内容について、 …
-
 【文学部、国際・外国語学部】小論文の頻出テーマと対策をスタサプ講師が解説!
【文学部、国際・外国語学部】小論文の頻出テーマと対策をスタサプ講師が解説!学部によって書き方やテーマが異なる小論文。 対策として過去問を演習することはもちろんだが、目指す大学や学部の出題傾向に応じた社会課題やその背景にある歴史、国際情勢にも視点を向け知識を蓄えていきたいところだ。 今回は文学部、国際・外国語学部の小論文対策を紹介。 現代文・小論文講師の小柴先生による論理的 …
-
 【心理学系分野】小論文&志望理由書対策のおすすめ本をスタサプ講師が解説!
【心理学系分野】小論文&志望理由書対策のおすすめ本をスタサプ講師が解説!小論文や、総合型選抜・学校推薦型選抜の対策には読書がいいというけれど、実際どんな本を読んだらいいんだろう? そんな人のために、スタディサプリで「現代文」と「小論文」を担当する小柴大輔先生が読書案内をしてくれるコーナーがスタート! 今回は、心理学系分野の本を紹介してもらったよ。 教育・幼児教育・福祉・ …
-
 コンサルで問題解決&環境と肌に優しい化粧品づくりを!【街頭で先輩を直撃 チェッキュー12】
コンサルで問題解決&環境と肌に優しい化粧品づくりを!【街頭で先輩を直撃 チェッキュー12】将来について考えたとき、「やりたいことがわからない…」という高校生も多いはず。 「チェッキュー12」では、夢を見つけて動き出した現役大学生&専門学生たちを街頭で直撃! 先輩たちが「今学んでいること」や「進路を決めたきっかけ」を、自分自身も進路に迷ったこともある学生編集部が聞いて …
-
 イルカトレーナー&小学校の先生になりたい!【街頭で先輩を直撃 チェッキュー12】
イルカトレーナー&小学校の先生になりたい!【街頭で先輩を直撃 チェッキュー12】将来について考えたとき、「やりたいことがわからない…」という高校生も多いはず。 「チェッキュー12」では、夢を見つけて動き出した現役大学生&専門学生たちを街頭で直撃! 先輩たちが「今学んでいること」や「進路を決めたきっかけ」を、自分自身も進路に迷ったこともある学生編集部が聞いて …


